夁嫀偺偊偭偣偄
傏傫偡偨偑夁嫀偵朸強偵搳峞偟偨偊偭偣偄傪宖嵹偟傑偡丅
摉帪偺暥復偺尨暥偦偺傑傑偱偡丅
挊嶌尃忋丄栤戣偺偁傝偦偆側偊偭偣偄偼妱垽偟傑偟偨丅
仧 2005擭03寧22擔(壩)丂乽偝偔傜乮撈彞乯乿偺暘愅
仧 2005擭02寧03擔(栘)丂僺僢僠偼桭忣丄僴乕儌僯乕偼垽忣
仧 2004擭03寧03擔(悈)丂旤偟偄擔杮偺壧
仧 2003擭11寧21擔(嬥)丂僺僇僜丒僋儔僔僢僋
仧 2003擭10寧27擔(寧)丂働儞僞僢僉乕偑憱傞棟桼
仧 2003擭10寧02擔(栘)丂嵟廔廃偺戞係僐乕僫乕
仧 2003擭09寧16擔(壩)丂僴僗儔乕偵偮偄偰乮俀乯
仧 2003擭09寧01擔(寧)丂僴僗儔乕偵偮偄偰乮侾乯
仧 2003擭07寧30擔(悈)丂僎僱僾儘偺堄枴
仧 2003擭07寧25擔(嬥)丂捖晠側恖惗榑
仧 2003擭07寧08擔(壩)丂墘憈偺嬻婥
仧 2003擭06寧10擔(壩)丂壒偺僀儊乕僕
仧 2003擭06寧05擔(栘)丂敿壒偺鏰乮偒偟乯傒
仧 2003擭05寧26擔(寧)丂巕壒偺張棟偵偮偄偰

|
仧 2005擭03寧22擔(壩)丂乽偝偔傜乮撈彞乯乿偺暘愅
|
乽弔傑偮傝乿偵岦偗偰丄乽偝偔傜乮撈彞乯乿傪尰嵼楙廗偟偰偄傞丅偙偺嬋偑幚
嵺偵俰亅俹倧倫偺堦嬋偲偟偰僸僢僩偟偨偲偒丄杔傕旕忢偵婥偵擖偭偰僔儞僌儖
俠俢傪峸擖偟丄僇儔僆働偱斺業偟偨傝偟偰偄偨丅
偍寛傑傝偺僐乕僪恑峴偲壧帉偺惵廘偝偑丄杔偺僴乕僩偵傕僸僢僩偟偨傢偗偱偁
傞偑丄夵傔偰偙偺嬋傪岥偢偝傫偱傒傞偲柺敀偄偙偲偑傢偐偭偨丅
偙偺嬋偼丄擔杮岅偺僀儞僩僱乕僔儑儞乮搶嫗曽尵偺堄枴乯傪偐側傝惓妋偵側偧偭
偰偄傞偺偱偁傞丅埲壓偵僒價偺晹暘偩偗傪愗傝弌偟偰帵偟偰傒傞丅
亂撉傒亃偝仾偔仺傜丂偝仾偔仺傜丂偄伀偞丂晳仾偄仺忋仺偑伀傟
亂壧亃丂偝仾偔仺傜丂偝仾偔仺傜丂偄伀偞丂晳仾偄仺忋仾偑伀傟
丂仾丗師偺壒偺壒偺崅偝偑忋偑傞
丂仺丗師偺壒偺壒偺崅偝偵曄壔側偟乮暥柆偵傛偭偰懡彮偺忋壓偼偁傝乯
丂伀丗師偺壒偺壒偺崅偝偑壓偑傞
亂撉傒亃偼丄晛捠偵擔杮岅偺僀儞僩僱乕僔儑儞偱楴撉偟偨応崌偺壒偺崅偝偺曄
壔丄亂壧亃偼怷嶳捈懢楴偺壧偺儊儘僨傿乕偵偍偗傞壒偺崅偝偺曄壔偱偁傞丅
偙傟傪尒傞偲丄堦売強傪彍偒丄亂撉傒亃偲亂壧亃偑姰慡偵堦抳偟偰偄傞偺偑傢
偐傞丅
忋婰偱偼僒價偺晹暘偩偗愗傝弌偟偰傒偨偑丄嬋慡斒偺偐側傝偺晹暘偱亂撉傒亃
偲亂壧亃偺堦抳傪尒傞偙偲偑弌棃傞丅
懳徠揑側椺偲偟偰丄埲壓偵乽偝偔傜乮撈彞乯乿偲帡偨姶偠偺嬋偱偁傞挿熀崉偺
乽姡攖乿傪帵偟偰傒傞丅
亂撉傒亃偐仾傫仺傁仺偄丂偄伀傑丂偒仾傒仺偼丂偠伀傫仺偣仺偄仺偺
亂壧亃丂偐仾傫仾傁仺偄丂偄伀傑丂偒伀傒伀偼丂偠伀傫仾偣仾偄仾偺
挿熀僼傽儞偵偼怽偟栿側偄偑丄乽偝偔傜乮撈彞乯乿偵偍偗傞堦抳偵偼掱墦偄傕
偺偑偁傞丅
昁偢偟傕亂撉傒亃偲亂壧亃偑堦抳偟偰偄傞曽偑桪傟偰偄傞偲偄偆傢偗偱偼側偄
偑丄乽偝偔傜乮撈彞乯乿偼偦偺揰偵偍偄偰偐側傝峫椂偝傟偨嬋偱偁傝丄偦偺
乽堦抳乿偑儊儘僨傿乕偑帺慠偵暦偙偊傞棟桼偺堦偮偵側偭偰偄傞偺偐傕偟傟側
偄丅
|
仾儁乕僕偺愭摢傊
|
仧 2005擭02寧03擔(栘)丂僺僢僠偼桭忣丄僴乕儌僯乕偼垽忣
|
傕偆侾儢寧偑宱偭偰偟傑偆偑丄侾寧俁擔偵傾儞僒儞僽儖丒僇儁儔偺墘憈夛偵峴偭
偨丅奐応乮栚崟偺嫵夛乯偵憗偔拝偒偡偓偰偟傑偭偨偨傔丄嬤偔偺媔拑揦偱帪娫
傪捵偟偨丅婥偑偮偔偲丄奐応帪娫偐傜侾侽暘傎偳宱偭偰偟傑偭偰偄偰丄屻傠偺
曽偺惾偵嵗偭偰暦偔偙偲偵側偭偰偟傑偭偨丅
傾儞僒儞僽儖丒僇儁儔偼丄朷寧愭惗偺強懏偡傞傾儞僒儞僽儖丒僌儖乕僾偱丄偙
傟傑偱偵俆夞埲忋偼墘憈夛傪暦偄偰偄傞丅偟偐偟丄崱夞偺傛偆偵屻傠偺曽偺惾
偱暦偄偨偙偲偼側偔丄僾儘偲偼偄偊彮恖悢側偺偱偳偆側傞偺偐偑怱攝偱偁偭偨丅
偟偐偟丄偦傫側怱攝偼柍梡偱偁偭偨丅壧偄弌偟偐傜奺僷乕僩偺梟偗崌偭偨惡偑
旤偟偄嬋慄傪昤偔傛偆偵丄傑偨丄慡懱偺僴乕儌僯乕偑娵偄廮傜偐側夠偲側偭偰
杔偺帹偵撏偄偰偒偨丅
杔偼乮幾擮偑偁傞偺偐乯攞壒傪暦偒庢傞偙偲偑嬯庤側偺偩偑丄嬋偑屻敿偵嬋偑
恑傓偵偮傟偰丄僺僢僐儘偺傛偆側壒怓偺懚嵼偟側偄偼偢偺壒偑揤堜嬤偔偵懚嵼
偟巒傔丄傾儞僐乕儖偱墘憈偝傟偨僕儑僗僇儞偺 "Ave Regina Caelorum" 偵帄
偭偰偼丄偆傞偝偄偔傜偄偵攞壒偑暦偙偊偰偒偨丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仦丂丂丂仦丂丂丂仦
乽僺僢僠偼桭忣丄僴乕儌僯乕偼垽忣乿丅朸桳柤崌彞巜婗幰偑偍偭偟傖偭偨尵梩
傜偟偄丅擭枛偵恖偯偰偵暦偄偰偐傜丄杔偺怱偵偄偮傑偱傕巆偭偰偄傞丅
崌彞偵偍偄偰丄捠忢偺暲傃偱偼丄嬤偔偺恖偼摨偠慁棩傪壧偭偰偄傞偼偢偱偁傞丅
嬤偔偺恖偲僺僢僠傪崌傢偣傞偨傔偵偼丄乽桭忣乿偑昁梫偱偁傞丅丅丅偲偄偆堄
枴側偺偩傠偆偐丠
偦傟偵懳偟丄墦偔偄傞暿偺壒傪弌偟偰偄傞恖偲僴乕儌僯乕乮攞壒乯傪嶌傝弌偡
偨傔偵偼丄乽垽忣乿偑昁梫偱偁傞丅丅丅偲偄偆堄枴側偺偩傠偆偐丠
杔偵偼傕偭偲怺偄堄枴偑崬傔傜傟偰偄傞傛偆側婥偑偟偰側傜側偄丅
偄偢傟偵偟偰傕丄摿偵崌彞壒妝偲偄偆偺偼丄儊儞僞儖側柺丄僼傿僕僇儖側柺偑
僗僩儗乕僩偵墘憈偵尰傟傞寍弍偩偲巚偆丅偪傚偭偲堄幆傪曄偊傞偩偗偱丄墘憈
偵柦偑悂偒崬傑傟傞弖娫傪壗搙傕尒偰偒偨偟丄偙傟偐傜傕偦偆偄偆弖娫偵棫偪
夛偊傞偙偲傪婅偭偰偄傞丅偩偐傜崌彞偼傗傔傜傟側偄丅
|
仾儁乕僕偺愭摢傊
|
仧 2004擭03寧03擔(悈)丂旤偟偄擔杮偺壧
|
丂愭擔丄埲壓偺俠俢傪峸擖偟偨丅
丂仜乽旤偟偄擔杮偺壧乿[AVCL-25401]
丂乥壧丂丂丗攇懡栰杛旤
丂乥僺傾僲丗栰暯堦榊
丂乥嬋栚丂丗偐傜偨偪偺壴乛拞崙抧曽偺巕庣壧乛偙偺摴乛廐偺寧乛昹曈偺壧乛
丂乥丂丂丂丂偪傫偪傫愮捁乛忛儢搰偺塉乛偝偔傜墶偪傚偆乛壞偺巚偄弌乛
丂乥丂丂丂丂偨偁傫偒傏乕傫偒乛柖偲榖偟偨乛愥偺崀傞傑偪傪乛傗偼傜偐偵乛
丂乥丂丂丂丂偄偺偪側偒乛壴偺奨乛巕庣壧乛偝偔傜墶偪傚偆乛棊梩徏
丂攇懡栰杛旤偝傫偼丄慜嶌偺傾儖僶儉乽傾儖僼僅儞僔乕僫偲奀乿乮壧丗攇懡栰
杛旤乛敽憈丗偮偺偩偨偐偟乯偱丄偦偺壧惡偵枺椆偝傟偰偄偨偺偩偑丄偙偺傾儖
僶儉偼丄攇懡栰偝傫偵偼捒偟偔擔杮岅偺壧偺傒偱峔惉偝傟偰偄傞丅
仈乽棊梩徏乿偼崌彞嬋偱偍側偠傒偺彫椦廏梇嶌嬋偺嶌昳丅尦偼壧嬋傜偟偄丅
丂杔偼丄惡妝壠偺壧偆擔杮壧嬋偲偄偆傕偺偵偼丄偳偆偟偰傕撻愼傔側偄丅偳偆
偟偰傕嵟廔揑偵惡帺枬偵側偭偰偟傑偄丄擔杮岅偑擔杮岅偲偟偰揱傢偭偰棃側偄
墘憈偑懡偄偐傜偱偁傞丅乮曃尒偐傕偟傟側偄偑乯
丂偟偐偟堦嬋栚偺乽偐傜偨偪偺壴乿偺侾僼儗乕僘傪帹偵偟偨偩偗偱丄偦偺怱攝
偼姰慡偵暐怈偝傟偨丅攇懡栰偝傫偺壧彞傪彑庤偵暘愅偟偰偟傑偆偲丄埲壓偺俁
偮偺摿挿偑偁傞丅
乮侾乯曣壒偱墴偝側偄丄偐偮丄巕壒傪戝愗偵壧偆
乮俀乯壒偑徚偊傞弖娫傑偱嵶怱偺拲堄偑暐傢傟偰偄傞乮擔杮岅偼尨懃曣壒廔巭乯
乮俁乯曣壒偲曣壒偺偮側偘曽偑愨柇乮椺丗偁偍偄乧偁偍偄乯
丂忋婰偺偳偺梫慺傕丄擔杮岅傪擔杮岅傜偟偔暦偙偊偝偣傞偁傞庬偺僥僋僯僢僋
偲尵偊側偔傕側偄偺偱偁傞偑丄帺暘偑擔杮岅偺崌彞嬋傪壧偆応崌偵傕丄廫暘墳
梡偡傞偙偲偑弌棃傞傛偆側婥偑偡傞丅
丂偲丄乽偐傜偨偪偺壴乿偺帊傪夵傔偰挱傔偰偄偰傆偲婥晅偄偨偙偲偑偁傞丅慡
晹偱俇楢偐傜側傞杒尨敀廐偺偙偺桪傟偨帊偵偼丄乽偆乿偺曣壒傪帩偮尵梩偑堦
搙偲偟偰搊応偟側偄丅戝敪尒偐傕偟傟側偄丅
丂丂丂丂丂丂丂侓偐傜偨偪偺偦偽偱媰偄偨傛
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂傒傫側傒傫側傗偝偟偐偭偨傛
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮乽偐傜偨偪偺壴乿戞俆楢傛傝乯
|
仾儁乕僕偺愭摢傊
|
仧 2003擭11寧21擔(嬥)丂僺僇僜丒僋儔僔僢僋
|
丂岲偒側夋壠傪俁恖嫇偘傠偲尵傢傟偨傜丄僺僇僜丄僄僢僔儍乕丄壀杮懢榊偲尵
偆偲巚偆丅嶌昳孮傪尒傞偲丄俁恖偲傕弮悎偵夋壠偲偄偊傞偐偳偆偐偼媈栤偩偑丅
丂愭擔丄忋栰偺怷旤弍娰偱奐嵜偝傟偰偄傞乽僺僇僜丒僋儔僔僢僋乿偵峴偭偰棃
偨丅僺僇僜偼丄偦偺挿偄惗奤偱忢偵嶌昳傪憂嶌偟懕偗偨懡嶌偺夋壠偱偁傞丅僺
僇僜揥側偳偲尵偆偲丄傢偗偺傢偐傜側偄嶌昳傪尒廔傢偭偨崰偵偼丄偖偭偨傝偟
偰偟傑偆偺偑忢偱偁傞丅偩偑丄偙偺揥棗夛偼丄屻偵乽怴屆揟庡媊乿偲屇偽傟傞
傛偆偵側傞帪婜乮1914擭乣1925擭乯偺嶌昳偺傒傪廤傔偨旕忢偵儐僯乕僋側婇夋
偱偁傝丄揥帵嶌昳偺検傕挌搙偄偄丅
丂僺僇僜偲尵偊偽丄偳偆尒偰傕恖娫偵偼尒偊側偄彈惈偺奊傗丄愴憟偺嫲傠偟偝丄
嬸偐偝傪僗僩儗乕僩偵昤偄偨嶌昳乻僎儖僯僇乼側偳偑桳柤偱偁傞偑丄偙偺帪婜
偺嶌昳偼偲偰傕暘偐傝傗偡偔丄僞僢僠偑旕忢偵旤偟偄丅偙偺帪婜偼丄僺僇僜偵
偲偭偰嵟傕岾偣側帪婜偩偭偨傜偟偔丄嶌昳偵傕戝偄偵斀塮偝傟偰偄傞偺偩偦偆
偩丅
丂崱夞揥帵偝傟偰偄偨嶌昳偺拞偱丄杔偑崱夞嵟傕報徾偵巆偭偨嶌昳偼丄乻愹偺
傎偲傝偺俁恖偺彈乼偲偄偆戣柤偺嶌昳偱丄妼怓偺扨怓偱偐側傝戝偒側僒僀僘
乮200亊161cm乯偺奊偩偭偨丅偙偺嶌昳偱栚傪堷偄偨偺偼丄俁恖偺彈惈偺庤偱丄
僌儘乕僽偺傛偆偵傕尒偊傞庤側偺偱偁傞偑丄偦偙偐傜廮傜偐偝偲椡嫮偝偑姶偠
傜傟旕忢偵僀儞僷僋僩偑偁偭偨丅
丂傑偨丄偙偺戝嶌乻愹偺乣乼偺廃傝偵偼乽乻愹偺乣乼偺廗嶌乿偲偄偆戣柤偺奊
偑俆揰揥帵偟偰偁偭偨丅俁揰偼戝嶌偺庤偺傒偺奊丄侾揰偼戝嶌慡懱偺僗働僢僠
偺傛偆側奊丄侾揰偼侾斣塃懁偵埵抲偡傞侾恖偺彈惈偺婄偺傒偺奊偱偁偭偨丅
丂杔偼奊傪廗偭偨偙偲偑側偄偺偱奊偺惂嶌夁掱偺偙偲偼慡偔傢偐傜側偄丅偟偐
偟丄偁偺揤嵥僺僇僜偑侾偮偺嶌昳傪昤偒忋偘傞傑偱偵丄奺僷乕僣偺楙廗傪孞傝
曉偟偰丄偁偁偱傕側偄偙偆偱傕側偄乮幚嵺乽廗嶌乿偲戝嶌乻愹偺乣乼偺姰惉偝
傟偨奊偺僷乕僣偼柧傜偐偵堘偭偰偄傞乯偲擸傒側偑傜昤偄偰偄偨偲偄偆帠幚偵
嬃偄偨丅
丂偦偙偱傆偲丄偙傟偼壒妝偵偍偄偰偼丄嬋傪嶌傝忋偘偰偄偔夁掱偲慡偔摨偠側
偺偱偼側偄偐偲巚偭偨丅堦偮偺慁棩乮傕偭偲嬊強揑偵偼堦偮偺壒偺挼桇乯傪偁
偁偱傕側偄偙偆偱傕側偄偲擸傒嬯偟傒丄帺暘偑擺摼弌棃傞抜奒傑偱崅傔傞乮傛
偆搘椡偡傞乯偲偙傠偐傜巒傑傝丄嵟廔揑偵偼嬋慡懱偱惗偐偣傞傛偆偵偵側傞傑
偱傕偑偒懕偗傞偺偑丄壒妝偺憂嶌夁掱側偺偱偼側偄偐偲丅
丂挿偄娫丄岲偒偱壒妝傪懕偗偰偄傜傟傞偺偼丄偙偺乽偁偁偱傕側偄偙偆偱傕側
偄乿偺夁掱偑偁傞偐傜側偺偩偲丄崱峏側偑傜嵞敪尒偟偨偺偱偁偭偨丅
|
仾儁乕僕偺愭摢傊
|
仧 2003擭10寧27擔(寧)丂働儞僞僢僉乕偑憱傞棟桼
|
丂尰嵼丄愳嶈巗巗柉儈儏乕僕傾儉偺僀儀儞僩偵岦偗偰丄"My Old Kentucky Home"
楙廗偟偰偄傞偑丄偳偆偟偰傕 "in the Old Kentucky Home" 偺偲偙傠偱抝惡偑
憱偭偰偟傑偆丅杔傕崌彞傪巒傔偨崰偼丄娫堘偄側偔憱偭偰偟傑偭偰偄偨偩傠偆丅
丂側偤憱傞偺偩傠偆丠偲偠偭偔傝峫偊偰傒偰丄傆偲埲慜撉傫偩堦嶜偺杮偵僸儞
僩偑塀偝偣偰偄傞傛偆側婥偑偟偨丅
丒乽奜崙岅偲偟偰偺擔杮岅乿乮挊丗嵅乆栘悙巬乯乵島択幮尰戙怴彂乶
偙偺杮偼丄斾妑尵岅妛偺尋媶幰偱偁傞挊幰偑丄棷妛惗偵擔杮岅傪嫵偊傞嵺偺宱
尡側偳傪怐傝岎偤側偑傜丄擔杮岅傪堦偮偺奜崙岅偲偟偰懆偊偰傾僾儘乕僠偟偰
偄傞側偐側偐柺敀偄撉傒暔偱偁傞丅
丂偙偺杮偱丄擔杮岅偺儕僘儉偵偮偄偰尵媦偟偰偄傞売強偑偁傞丅
亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅
擔杮岅偺壒愡偺挿偝偼乽攺乿偲偄偆扨埵偱悢偊傜傟傞丅乽偐偝乿偼擇壒愡偱擇
攺丄乽偐乿偲乽偝乿偲偄偆攺偼摨偠挿偝偩丅堦攺偺挿偝偑慡偰摨偠挿偝偵側傞
偲偄偆偺傕丄擔杮岅偺摿挜偩傠偆丅乵戞侾復丂擔杮岅傃壒偼偙偙偑堘偆亅壒惡乶
亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅
偙偺晹暘傪偐偮偰撉傫偩偲偒丄杔偼偡偖偵怓乆側擔杮岅傪摉偰偼傔偰傒偰丄
忋婰偺偙偲偑帠幚偱偁傞偙偲傪抦傝丄嬃湵偟偨偺傪妎偊偰偄傞丅
丂偙偙偱杮戣偵栠傝丄"Kentucky" 傪埲壓偺傛偆偵僇僞僇僫昞婰偟偰傒傞丅
働丒儞丒僞丒僢丒僉丒乕
侾丂俀丂俁丂係丂俆丂俇
杔傜偑乽働儞僞僢僉乕乿傪晛捠偵擔杮岅偲偟偰挐傞偲丄忋婰偺傛偆偵俇攺偺儕
僘儉偵側偭偰偟傑偆丅偟偐傕峏偵乽働儞僞僢僉乕乿偲偄偆尵梩偼丄偁偺僼儔僀
僪僠僉儞偺夛幮偺偍偐偘偱丄偲偰傕恎嬤側尵梩偲偟偰擔杮岅偺拞偵梟偗崬傫偱
偟傑偭偰偄傞偺偱丄峏偵偨偪偑埆偄丅擔杮岅偺偙偺俇攺偺儕僘儉偺姶妎傪幪偰
偢偵丄塸岅偭傐偔敪壒偟傛偆偲偡傞偲丄寢壥揑偵媫偄偩姶偠偵側偭偰偟傑偆丅
偮傑傝丄壧偵偡傞偲憱偭偰偟傑偆偺偱偁傞丅
丂嫮堷偱偁傞偑丄埲壓偺傛偆偵昞婰偟偰撉傫偱傒傞偲丄懡彮俇攺偺儕僘儉偺姶
妎偐傜懡彮側傝偲傕棧傟傞偙偲偑弌棃傞偱偼側偄偩傠偆偐丠
働丒僃丒儞丒僞丒傽丒僢丒僉丒傿丒僀
抝惡偺奆偝傫丄偍帋偟偁傟丅
|
仾儁乕僕偺愭摢傊
|
仧 2003擭10寧02擔(栘)丂嵟廔廃偺戞係僐乕僫乕
|
丂愭擔丄崅峑帪戙偺桭恖偑僐儞僒乕僩儅僗僞乕傪柋傔傞晎拞巗柉岎嬁妝抍偺掕
婜墘憈夛傪暦偒偵峴偭偨丅墘憈傪暦偔偺偼擇搙栚側偺偱丄僆働偺幚椡偼戝懱傢
偐偭偰偄偨乮巗柉僆働偲偟偰偼憡摉崅偄儗儀儖乯偺偩偑丄墘憈傪暦偄偰夵傔偰
巚偭偨偙偲偑偁偭偨丅偦傟偼丄墘憈幰偺堦偮堦偮偺壒偵懳偡傞廤拞椡偺惁傑偠
偝偱偁傞丅妋偐偵丄僾儘偺墘憈偺傛偆偵丄忢偵壒偑寛傑傞傢偗偱偼側偄丅偟偐
偟丄俆侽暘嬤偔偐偐傞岎嬁嬋乮偙偺擔偺墘栚偼僪儃儖僓乕僋偺乽怴悽奅傛傝乿乯
傪慜偵丄懨嫤偡傞偙偲側偔忢偵椙偄壒傪弌偦偆偲偡傞墘憈幰偺巔偵偼丄怱傪懪
偨傟偨丅
丂榖偼撍慠曄傢傞丅杔偼偦傟傎偳塣摦傪偟側偄偺偩偑丄僗億乕僣娤愴乮庡偵僥
儗價乯偑戝岲偒偱偁傞丅悽奅悈塲丄悽奅棨忋側偳丄擔杮恖慖庤偺嵟嬤偺妶桇偵
偼栚傪尒挘傞傕偺偑偁傝丄偮偄偮偄栭拞傑偱拞宲傪尒偰偟傑偄丄師偺擔偵偼丄
柊偄栚傪偙偡傝側偑傜弌嬑偲側偭偰偟傑偭偰偄傞丅
丂嵟嬤丄僗億乕僣奅偱妶桇偟偰偄傞斵傜傪尒偰偄傞偲丄愄偺傛偆側擔偺娵傪攚
晧偆偙偲偵傛傞僾儗僢僔儍乕偐傜棃傞斶憇姶傪傎偲傫偳姶偠側偄丅偦偺偙偲偑
岠偄偰偄傞偺偐丄偙偙悢擭杮摉偵杮斣偵嫮偄丅偍偦傜偔丄墷暷敪偺壢妛揑僩儗
乕僯儞僌乛儊儞僞儖僩儗乕僯儞僌偲丄尦乆抦宐偱彑晧偡傞擔杮偺偍壠寍偲偑丄
挌搙椙偄僶儔儞僗偱梈榓偟偰偄傞偐傜側偺偱偼側偄偩傠偆偐丅嫞媄屻偺僀儞僞
價儏乕側偳傪暦偔偲丄寢峔彫偝側儈僗偼偟偰偄傞偺偩偑丄偦偺儈僗傪儕僇僶儕
偡傞怱偺梋桾偑偁傞偨傔丄儈僗傪偡傜媡偵椡偵曄偊偰偟傑偆偙偲偑偁傞傛偆偩丅
丂寢嬊偺偲偙傠丄壒妝偵偟偰傕僗億乕僣偵偟偰傕丄杮斣偱椡傪敪婗偡傞偨傔偵
偼丄廤拞椡傪搑愨偊傞偙偲側偔帩懕偟丄婲偙偭偨帠徾偵懳偟傕椻惷偵敾抐偱偒
傞偙偲偑昁梫側偺偩偲巚偆丅尵偆偼堈偟偱偁傞偺偩偑丅丅丅
丂柍棟栴棟丄崱夞偺俁嬋乮壽戣嬋亊侾丄帺桼嬋亊俀乯傪僩儔僢僋嫞媄偵偨偲偊
偰傒傞丅崱夞偼椺擭偵傕憹偟偰堦嬋堦嬋傪壧偆偺偵懱椡傪梫偡傞偺偱丄係侽侽
倣亊俁偺儕儗乕傪堦恖偱憱傝懕偗傞偲偄偆偺偱偼偳偆偩傠偆偐丅
乮幚嵺偺棨忋嫞媄偱偼係侽侽倣亊係儕儗乕偟偐側偄丅乯
丂帺暘埲奜偺僠乕儉偺戞侾丄戞俀憱幰偼偄偢傟傕戞係僐乕僫乕偱儔僗僩僗僷乕
僩偡傞偨傔丄堦恖偱憱偭偰偄傞帺暘傕丄侾廃栚丄俀廃栚丄偄偢傟傕儔僗僩僗僷
乕僩偟側偗傟偽棧偝傟偰偟傑偆偍偦傟偑偁傞丅偟偐偟丄杮摉偺彑晧偼戞俁憱幰
乮傾儞僇乕乯偲偺彑晧偱偁傞丅僩儔僢僋傪俀廃係暘偺俁憱偭偰傕丄嵟屻偵弌偣
傞椡偑側偗傟偽丄嵟屻偺戞係僐乕僫乕偱愴偄偵攕傟偰偟傑偆偙偲偵側傞丅
丂崱擭偙偦丄嵟廔廃偺戞係僐乕僫乕偱丄崅傜偐偵壧偄忋偘偨偄丅
丂丂Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.
丂丂丂丂丂丂丂劅劅劅丂惞楈偲偲傕偵丄晝側傞恄偺塰岝偺偆偪偵丅傾乕儊儞丅
|
仾儁乕僕偺愭摢傊
|
仧 2003擭09寧16擔(壩)丂僴僗儔乕偵偮偄偰乮俀乯
|
丂崱夞偼僴僗儔乕偑壒妝巎忋偳偺傛偆側昡壙傪庴偗偰偄傞偐偵偮偄偰峫偊偰傒
傞丅巹偑帠偁傞偛偲偵嶲徠偟偰偄傞奆愳払晇偝傫偺挊嶌(*1)偺拞偱丄僴僗儔乕
偼俀売強乮偺傒乯偵搊応偡傞丅
乮侾乯儅僪儕僈乕儗偺崙劅僀僞儕傾
丂- 僴儞僗丒儗僆丒僴僗儔乕(1564-1612)丄僴僀儞儕僢僸丒僔儏僢僣(1585-1672)
丂丂偲偄偭偨師戙偺僪僀僣丒僶儘僢僋壒妝偺奐敪傪扴偆嶌嬋壠偨偪傕偙偺抧偵
丂丂棷妛偟偰偄傞丅乣丅乮搉曈拲丗乽偙偺抧乿亖乽償僃僱僣傿傾乿乯
乮俀乯壒妝傪曄偊偨廆嫵夵妚劅僪僀僣
丂- 偙偺悽婭屻敿偵側傞偲丄僐儔乕儖曇嬋偼偝傜偵廩幚偟偨傕偺偵側傝丄偲偔
丂丂偵僀僞儕傾偺媄朄傪摨壔偟偨僴儞僗丒儗僆丒僴僗儔乕(1564-1612)丄儈僴僄
丂丂儖丒僾儗僩儕僂僗(1571偙傠-1621) 傜偼戝婯柾側婍妝敽憈偮偒僐儔乕儖傪
丂丂嶌嬋偟偰偄傞丅乣丅乮搉曈拲丗乽偙偺悽婭乿亖乽16悽婭乿乯
丂- 僴僗儔乕偺嶌偭偨楒偺壧乹傢偑怱傒偩傟偝傢偓乺偺慁棩偑丄偦偺屻偵嫵夛
丂丂偺僐儔乕儖偲側傝丄僉儕僗僩偺庴擄傪偄偨傓乽寣挭偟偨偨傞庡偺屼摢乿偺
丂丂壧帉偵傛偭偰丄戝僶僢僴偺乹儅僞僀庴擄嬋乺偵傕岠壥揑偵梡偄傜傟偰偄傞
丂丂偺偼丄偁傑傝偵傕桳柤偱偁傞丅乣丅
乮侾乯偍傛傃乮俀乯傪慜屻偺娭學偐傜撉傒庢傞偲丄亀僀僞儕傾偺桪傟偨壒妝傪
偦偺摉帪壒妝偺屻恑崙偱偁偭偨僪僀僣偵帩偪崬傒敪揥偝偣偨亁丄亀僴僗儔乕
偺慁棩偼丄偐偺戝僶僢僴愭惗偑嵦梡偟媟岝傪梺傃偨亁偲偄偆暤埻婥偑昚偭偰偄
傞傛偆偵巚偊偰巇曽偑側偄丅傂偹偔傟偨夝庍傪偡傞偲丄僴僗儔乕偺嵥擻偑夁彫
昡壙偝傟偰偄傞傛偆偵尒偊傞偺偱偁傞丅幚嵺偵偼丄挊幰偱偁傞奆愳偝傫傕僴僗
儔乕偺惣梞壒妝偺敪揥偵偍偗傞峷專偵偮偄偰偼戝偄偵擣傔偰偄偰丄巻柺偺惂尷
偵傛傝丄媰偔媰偔僴僗儔乕偵娭偡傞婰弎傪妱垽偟偰偄傞偺偩偲怣偠偨偄偑丅
僶僢僴偺乹儅僞僀庴擄嬋乺偺拞偱丄僴僗儔乕偺慁棩偼壗売強偵傕偪傝偽傔傜傟
偰偄傞(*2)丅幚偵旤偟偄慁棩偱偁傞丅僴僗儔乕偺嶌偭偨楒偺壧傪僀僄僗偺廫帤
壦偺応柺偵巊梡偟偰偟傑偆偁偨傝偼丄僶僢僴偺執戝偝偵傕宧暈偡傞丅偟偐偟丄
僴僗儔乕偺僆儕僕僫儖偺慁棩偑側偗傟偽丄偁偺庫嬍偺乹儅僞僀庴擄嬋乺帺懱丄
懚嵼偟側偐偭偨偺偱偁傞両
僴僗儔乕偺壒妝偼丄僔儏僢僣丄僶僢僴丄儀乕僩乕償僃儞丄僽儔乕儉僗偲庴偗宲
偑傟丄僪僀僣偺壒妝偵柆乆偲棳傟懕偗偰偄傞偙偲傪媈偆梋抧偼側偄偺偱偁傝丄
擔杮偱傕傕偭偲昡壙偝傟偰傕椙偄偺偱偼側偄偐偲巚偆偺偱偁傞丅
(*1)乽拞悽丒儖僱僒儞僗偺壒妝乿乮挊丗奆愳払晇乯乵島択幮尰戙怴彂乶
(*2)亂暥專亃乽儅僞僀庴擄嬋乿乮挊丗釫嶳丂夒乯乵搶嫗彂愋乶
丂丂亂妝晥亃乽儅僞僀庴擄嬋乿乵慡壒妝晥弌斉乶
|
仾儁乕僕偺愭摢傊
|
仧 2003擭09寧01擔(寧)丂僴僗儔乕偵偮偄偰乮侾乯
|
丂"Dixit Maria" 娭楢偱崱庢傝慻傫偱偄傞嶌嬋壠僴僗儔乕乮HASSLER,Hans Leo丄
1564乣1612丄僪僀僣乯偲偺弌夛偄偼丄巹偑崌彞傪巒傔偰敿擭掱偟偨崰偵丄摉帪
偺妛惗巜婗幰偑乽僴僗儔乕悽懎嬋廤乿偲偄偆僗僥乕僕傪慻傒丄偦偺楙廗傪巒傔
偨偲偒丄栺侾俉擭慜乮両乯偱偁傞丅乮摨偠崰丄偨傑偨傑價儕儎乕僪傪傔偖傞恖
娫柾條傪昤偄偨塮夋乽僴僗儔乕俀乿偑岞奐偝傟丄奨偱傕價儕儎乕僪偑棳峴偭偰
偄偨丅乯
丂乽僴僗儔乕悽懎嬋廤乿偲偄偆僗僥乕僕傪捠偠偰偼丄巹偼摿偵偙偺嶌嬋壠偵嫽
枴傪帩偮偙偲偑側偐偭偨丅僪僀僣岅偩偭偨偺偱尵梩偱惛堦攖偩偭偨偐傜偐傕偟
傟側偄丅偟偐偟丄僴僗儔乕傪壧偭偰悢儢寧宱偪丄桭恖偵俀枃慻偺儗僐乕僪乮傑
偩俠俢偲儗僐乕僪偑敿乆偺帪戙乯傪庁傝偰丄帠懺偼媫曄偡傞丅
仜THE KING'S SINGERS' MADRIGAL HISTORY TOUR (EMI)
徴寕偩偭偨丅偦傟傑偱偼丄崌彞偲偼戝恖悢偺惡傪堦偮偵偡傞偙偲偵傛傞丄偄傢
偽壒埑偵傛傝恖傪姶摦偝偣傞傕偺偩偲怣偠崬傫偱偄偨偺偱偁傞偑丄偙偺儗僐乕
僪偵偼偦傟偲偼慡偔堘偆悽奅偑嬅弅偝傟偰偄偨丅壧偭偰偄傞偺偼偨偭偨偺俇恖
偺抝惈丅偟偐傕晛捠偺桪偟偦偆側偍偠偝傫丅偟偐偟丄斵傜偐傜敪偣傜傟傞壒妝
偼丄侾侽侽恖偺戝崌彞偱偼寛偟偰幚尰弌棃側偄姰帏側僴乕儌僯乕偑嶌傝弌偡壒
偺峀偑傝偱偁偭偨丅
偙偺傾儖僶儉偼丄僀僞儕傾丄僀僊儕僗丄僼儔儞僗丄僗儁僀儞丄僪僀僣偲儖僱僢
僒儞僗婜偺奺崙偺偄傢備傞儅僪儕僈儖傪僉儞僌僘丒僔儞僈乕僘偑壧偄傑偔偭偰
偄傞傕偺偱偁傞丅僪僀僣曇偱偼丄僴僗儔乕偺儅僪儕僈儖偑俀嬋徯夘偝傟偰偄傞丅
乮侾乯Tanzen und Springen乮梮偭偰丄偲傃挼偹偰乯
乮俀乯Ach weh des Leiden
乮侾乯偼慜弌偺乽僴僗儔乕悽懎嬋廤乿偺僗僥乕僕偱傕壧偭偨嬋偱偁傝丄乽僴僗
儔乕偲偄偊偽偙偺嬋両乿偲尵偆偔傜偄桳柤側儅僪儕僈儖偱丄妋偐偵柤嬋偱偁傞丅
乮巆擮側偑傜俇侽柤偺僗僥乕僕偱偼僉儞僌僘丒僔儞僈乕僘偺傛偆側寉夣偝偼弌
偣側偐偭偨偺偩偑丅乯
乮俀乯偼暿棧偺斶偟偝傪壧偭偨嬋偱偁傞偑丄偙偺俆惡偺嬋偑巹偺僴僗儔乕娤傪
戝偄偵曄偊偨丅斶偟偘側儊儘僨傿乕偲榓壒偺揥奐偑丄尵梩偑傢偐傜側偔偰傕僗
僩儗乕僩偵斶偟傒丄嬯擸傪偑揱偊偰棃傞丅弶傔偰暦偄偨崰偼丄壗搙傕壗搙傕偙
偺嬋傪暦偒懕偗偨傛偆側婰壇偑偁傞丅
侾俉擭偺帪偑宱偰丄"Dixit Maria" 傪壧偭偰傒偰傕姶偠偨偑丄僴僗儔乕偺嬋偼
儊儘僨傿乕偑旤偟偔幚偵傢偐傝傗偡偄丅偦偺曈偑椙偄堄枴偱傕埆偄堄枴偱傕懎
偭傐偝傪姶偠偝偣傞揰偱傕偁傞偺偩偑丄屄恖揑偵偙偺嶌嬋壠偼揤嵥敡偲偄偆傛
傝傕怑恖敡偺傛偆側婥偑偡傞丅偦傟備偊丄乽偙偺晹暘偼偙偺傛偆偵壧傢傟傞傋
偒乿偲偄偭偨丄暦偔懁偺梊憐傪棤愗傜側偄墘憈偑梫媮偝傟傞偺偩偲巚偆丅偦偆
偄偆揰偱偼丄寛偟偰擄嬋偱偼側偄偑丄墘憈偡傞偙偲偑擄偟偄偺偐傕偟傟側偄丅
|
仾儁乕僕偺愭摢傊
|
仧 2003擭07寧30擔(悈)丂僎僱僾儘偺堄枴
|
愭擔丄尰嵼僪僀僣偺僔儏僩僁僢僩僈儖僩乮Stuttgart乯偺戝妛偱丄廆嫵壒妝傪
曌嫮偟偰偄偰丄壞媥傒偱擔杮偵婣崙偟偰偄傞抦傝崌偄偵媣偟傇傝偵夛偭偨丅偦
偺偲偒偵丄僎僱僾儘乮[撈] General Prove乯偵偮偄偰偺丄嫽枴怺偄榖偑偁偭偨丅
僪僀僣偵偍偄偰丄僎僱僾儘偲偄偆偺偼丄埲壓偺傛偆側傕偺偩偦偆偱偁傞丅
乽悢擔慜偵丄杮斣摉擔偲慡偔摨偠恑峴偱偺墘憈夛偺僔儈儏儗乕僔儑儞傪峴側偆乿
僎僱僾儘偲偄偆尵梩偼丄擔杮偱傕嬤偄堄枴偱巊梡偝傟偰傞偑丄僪僀僣偱偼丄墘
憈奐巒帪娫丄僠働僢僩偺傕偓傝丄徠柧丄堖憰丄丄丄慡偰偵偍偄偰墘憈夛摉擔偝
側偑傜偵峴側偆偦偆偱偁傞丅摉慠丄僠働僢僩偼乽婾乮偵偣乯乿偺傕偺傪巊梡偟丄
桳柤側抍懱偺応崌偼丄僎僱僾儘偺擔偵妛惗岦偗偵埨壙乮偁傞偄偼僞僟乯偱婾僠
働僢僩傪攝晍偡傞応崌傕偁傞偲偄偆丅
僎僱僾儘偱偼墘憈夛偺摉擔捠傝偵恑峴偡傞偨傔丄墘憈傪巭傔傞偙偲偼側偔丄偦
偺擔偼墘憈幰偼楙廗傪偡傞偙偲偼弌棃側偄丅偦偺擔偵楙廗偡傞応崌偼丄慡偰偺
梊掕偑廔椆偟偨屻丄偍媞偝傫偵偼婣偭偰傕傜偄丄僟儊弌偟仌楙廗傪偡傞偦偆偱
偁傞丅
擔杮偱偼丄杮斣嬤偔偺儕僴乕僒儖偲偛偭偪傖偵側偭偰偄傞姶偠偑偡傞僎僱僾儘丅
杮摉偼丄墘憈夛慡懱傪懾傝側偔恑峴偝偣傞偨傔偺乮偄偐偵傕僪僀僣恖傜偟偄乯
僾儘僙僗偩偭偨偺偱偁傞丅
偝偰丄帺暘偨偪偼偙偺僎僱僾儘偲偄偆傕偺傪偳偺傛偆偵偲傜偊偨傜椙偄偐傪峫
偊偰尒傞丅崱擭搙偺妶摦偵嬶懱揑偵摉偰偼傔傞偲丄乽儂乕儖傪庁傝傞乿偲偄偆
娤揰偱偼丄俋寧侾俆擔乮寧丒廽乯偺崙嵺岎棳僙儞僞乕偱偺楙廗偑偦傟偵摉偨傞丅
堖憰傪拝偰僗僥乕僕偵棫偮昁梫偼側偄偲巚偆偑丄偙偺擔偺楙廗傪偳偺傛偆偵偲
傜偊傞偐偵傛偭偰丄僪僀僣棳偺僎僱僾儘偵側傞偐丄晛捠偺儂乕儖楙廗偵側傞偐
偑寛傑偭偰棃傞婥偑偡傞丅
屄恖揑偵偼丄偙偺擔偺楙廗偱偼乽僪僀僣棳偺僎僱僾儘乿偺婥帩偪偱椪傒偨偄傕
偺偱偁傞丅
|
仾儁乕僕偺愭摢傊
|
仧 2003擭07寧25擔(嬥)丂捖晠側恖惗榑
|
擇廡娫傎偳慜丄傾僇僨儈僢僔僃丒僇儁儗偺墘憈夛偵峴偭偨丅慡惾巜掕偩偭偨偑丄
弌墘偡傞桭恖偵棅傫偩偨傔丄慜偐傜俉楍栚偺戞堦償傽僀僆儕儞偺慜偱偁偭偨丅
戞堦僗僥乕僕偼崌彞偺擖傞儌乕僣傽儖僩偺乽懻姤儈僒乿偱偁傝丄旕忢偵儌乕僣
傽儖僩傜偟偄寉夣偱旤偟偄墘憈偩偭偨丅戞擇僗僥乕僕偼僆乕働僗僩儔偺傒偺墘
憈偱丄僽儔乕儉僗偺岎嬁嬋戞侾斣偱偁偭偨丅偙偺戞擇僗僥乕僕偱丄媣偟傇傝偵
僆乕働僗僩儔偺戠岉枴傪枴傢偆偙偲偑弌棃旕忢偵姶摦偟偨丅
慜偐傜俉楍栚偲偄偆偙偲偱丄弶傔偺偆偪偼乽壒嬁揑偵偼傕偆彮偟屻傠偺曽偑椙
偄乿偲巚偭偰偄偨偺偩偑丄暦偄偰偄偔偆偪偵傑傞偱帺暘偑償傽僀僆儕儞憈幰偺
堦堳偵側偭偨偐偺傛偆側嶖妎傪姶偠傞傛偆偵側偭偨丅
嬋偑恑傓偵偮傟偰丄慡偰偺墘憈幰偺嬋偵懳偡傞廤拞椡偺崅傑傝偲丄偦傟傪屻墴
偟偡傞巜婗幰偲偺娫偺怣棅娭學偲偄偆栚偵尒偊側偄巺偺懚嵼偑丄堦挳廜偺巹偵
傕嫮楏偵姶偠偰庢傟傞傛偆偵側偭偰偒偨丅僽儔乕儉僗偺戞係妝復偺庡戣嵞尰晹
偱偼丄巚傢偢椳偑堨傟偦偆偵側偭偰偟傑偭偨丅
僆乕働僗僩儔傪娫嬤偵尒偰丄僆乕働僗僩儔偵偍偗傞奒媺惂搙乮僸僄儔儖僉乕乯
傪巚偄弌偟偨丅
俁娗曇惉丄係娗曇惉偲嬋偵傛偭偰條乆偱偁傞偑丄娗妝婍偼嬋偵傛偭偰偼僗僥乕
僕偵棫偮偙偲偑弌棃側偄丅僫儞僶乕俆偺憈幰偱偁傟偽丄慡偰偺嬋偱僗僥乕僕偵
棫偮偙偲偑弌棃側偄丅
尫妝婍偺応崌偱傕丄崱夞偺儌乕僣傽儖僩偺傛偆偵嬋偺峔惉忋丄尫妝婍憈幰偺悢
偑尭傜偝傟傞応崌偑弌偰偔傞丅傑偨堦斒揑偵丄巜婗幰偵嬤偄慜偺楍偺恖偺曽偑
媄弍揑偵忋偱偁偭偨傝丄俀恖偱堦偮偺妝晥傪尒傞応崌丄晥傔偔傝傪偡傞恖偺曽
偑憡懳揑偵媄弍揑偵壓偱偁偭偨傝偡傞丅
崌彞偵栚傪揮偠偰傒傛偆丅堦斒揑偵崌彞偱偼慡堳暯摍偲偄偆晽挭偑偁傞丅巚偆
偵丄崌彞偺尨揰偼惞壧戉偱偁傝丄儓乕儘僢僷偵偍偄偰惞壧戉偵擖傟傞偲偄偙偲
偼丄壧偺僄儕乕僩偱偁偭偨偼偢側偺偱偁傞丅廬偭偰丄惞壧戉偵強懏偟偰偄傞帪
揰偱丄婛偵慖偽傟偟幰偱偁傝丄傑偟偰傗嫵夛偺拞乮恄偺屼慜乯側偺偱丄忋傕壓
傕偁傝摼側偄乮偼偢偱偁傞乯丅
椙偄傾儞僒儞僽儖偲偼壗偐丠偲峫偊傞偲丄婍妝偱傕崌彞偱傕丄偍屳偄傪偒偪傫
偲擣傔偁偄側偑傜丄帺暘偺栶妱傪慡偆偡傞偙偲偱偼側偄偩傠偆偐丅壗偩偐寢榑
偑捖晠側恖惗榑偺傛偆偵側偭偰偟傑偭偨偑丄偣傔偰壧偭偰傞偲偒偔傜偄偼乽捖
晠側恖惗榑乿偵増偄偨偄傕偺偱偁傞丅
|
仾儁乕僕偺愭摢傊
|
仧 2003擭07寧08擔(壩)丂墘憈偺嬻婥
|
偙偙偟偽傜偔丄惗乮側傑乯偱怓乆側墘憈傪暦偔婡夛偵宐傑傟偨丅僋儘僇儖憂棫
婰擮擔僐儞僒乕僩丄僐乕儖僔儍儞僥傿乕(6/20)丄EZ/Singers(6/21)丄搶嫗搒崌
彞嵳(6/28)丄擔棫CSP(7/5)丅墘憈媄弍偺桪楎偼偁偭偨傕偺偺丄偳偺墘憈傕偲偰
傕報徾偵巆傞傕偺偩偭偨丅
搨撍偱偁傞偑丄埲壓偵崌彞嬋偺嶌嬋壠偲偟偰偼崱傗戝屼強偺怴幚摽塸偝傫偺僄
僢僙僀傛傝乮柍抐偱乯堦暥傪堷梡偡傞丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仦丂丂丂仦丂丂丂仦
僺傾僯僢僔儌劅劅嘇
丒丒丒
丂偑丄偙偙偱丄傂偲偮崲傞偙偲偑偁傞丅偳傫側偵崅惈擻側儅僀僋傕巹偨偪偺帹
偺戙傢傝傪偟偰偔傟側偄偲偄偆偙偲偩丅墘憈夛応偱巹偨偪偑懱姶偱偒傞嬌尷揑
僺傾僯僢僔儌偼丄儅僀僋儘僼僅儞偱偼挻旝検偺揹棳偵岎姺偝傟傞偺傒偱偁傞丅
偦傟傪榐壒偟嵞惗偟偨偲偟偰丄巹偨偪偑挳偔偺偼扨側傞偐偡偐側壒偵偟偐偡偓
偢丄傊偨傪偡傞偲傎傫偲偆挳偙偊側偄戙暔偲側傞丅
丂偟偨偑偭偰捠忢偺俵俢乛俠俢僾儗乕儎乕丄嵞惗憰抲偱偼丄懱姶偡傞傎偐側偄
傛偆側僺傾僯僢僔儌傪挳偔偙偲偑偱偒側偄丅
丒丒丒
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂怴幚摽塸挊乽晽傪挳偔壒傪挳偔乿乮壒妝擵桭幮乯傛傝
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仦丂丂丂仦丂丂丂仦
搶嫗戝妛岺妛晹乮妋偐婡夿岺妛壢乯傪懖嬈偟偰偐傜搶嫗寍戝偺嶌嬋壢傪廋椆偟
偰偄傞挊幰傜偟偔丄偄偐偵傕側庯偺暥復偱偁傞丅愭擔偙偺暥復傪偨傑偨傑撉傫
偱丄旕忢偵嫟姶傪妎偊偨丅偦傟偲摨帪偵丄侾侽擭埲忋偐偗偰杮擻偺傑傑偵攦偄
偨傔偰偒偨帺暘偺晹壆偺俠俢偺嶳偑旕忢偵嬻嫊側傕偺偵巚偊偰棃偨丅
儔僀僽偵偼榐壒暔偐傜偼姶偠庢傟側偄乽墘憈偺嬻婥乿偑偁傞偲巚偆丅怴幚偝傫
偺尵偆嬌尷揑僺傾僯僢僔儌傕偦傟偲帡偨惈幙偺傕偺偱偼側偄偩傠偆偐丅
慺惏傜偟偄墘憈偺俠俢傪暦偄偨偲偒偺姶摦偲丄儔僀僽偱姶偠傞姶摦偲偼壗偐庬
椶偑堘偆傛偆側婥偑偡傞丅媄弍揑偵楎偭偰偄傞墘憈偱傕丄儔僀僽偱偼暿偺壗偐
偺椡偵傛傝姶摦傪摼傞偙偲偑傛偔偁傞丅
媄弍揑側岦忋傪捛偄媮傔傞偩偗偱側偔丄乽墘憈偺嬻婥乿偑壗傕偺偱偁傝丄偳偺
傛偆偵偟偨傜嶌傝弌偡偙偲偑弌棃傞偺偐傕偢偭偲峫偊偰備偒偨偄傕偺偱偁傞丅
|
仾儁乕僕偺愭摢傊
|
仧 2003擭06寧10擔(壩)丂壒偺僀儊乕僕
|
丂愭擔丄傾僼僞乕楙廗乮梫偡傞偵楙廗屻偺堸傒夛乯偱丄晥柺傪尒偰壧傪壧偆偲
偒丄偳偺傛偆偵壒傪僀儊乕僕偡傞偐偵偮偄偰偺榖偱惙傝忋偑偭偨丅僺傾僲偺尞
斦傪摢偵昤偔恖偑懡偐偭偨偺偼丄巕嫙偺崰僺傾僲傪廗偭偰偄偨恖偑懡偄偐傜偱
偁傠偆偐丅
丂杔偑帺傜偺堄巙偱壒妝傪巒傔偨偺偼丄拞妛峑偱僽儔僗僶儞僪晹偵擖晹偟偨偲
偒偩偲巚偭偰偄傞丅偦偺崰偼嬥娗妝婍傪悂偄偰偄偨丅嬥娗妝婍偵偼堦斒揑偵僺
僗僩儞偑俁杮乮傑偨偼係杮乯偟偐側偄丅偙傟偼尵偄姺偊傟偽丄摨偠巜偺忬懺偱
壗庬椶傕壒偑弌偰偟傑偆偲偄偆偙偲偱偁傞丅弶怱幰偼傑偢丄怬偺嬞挘丄懅偺検
偺挷惍側偳傪偁傟偙傟帋峴嶖岆偟偰丄乽壒掱乿傪嶌傝弌偡媄弍傪恎偵偮偗傞丅
惓偟偄壒掱偑嶌傝偝偣傞傛偆偵側偭偨傜丄師偼儕僘儉偱偁傞偑丄壒妝偼帪娫偲
偺愴偄側偺偱丄墘憈幰偺偙偲傪懸偭偰偼偔傟側偄丅偟偐傕摨偠塣巜偱暿偺壒偑
弌偰偟傑偆嬥娗妝婍偺応崌丄師偵棃傞壒傪忢偵僀儊乕僕偟丄壒偑敪偣傜傟傞傎
傫偺彮偟慜偵懱偺忬懺傪僀儊乕僕偟偨壒偑弌偣傞忬懺偵偟偰偍偐側偗傟偽側傜
側偄丅
丂榖傪尦偵栠偡偲丄杔偼晥柺傪尒偰壧傪壧偆偲偒丄摿偵妝婍偼摢偵昤偐側偄偑丄
師偵柭傞傋偒壒偺僀儊乕僕偼帩偭偰偄傞婥偑偡傞丅傑偨丄乽壒偑敪偣傜傟傞傎
傫偺彮偟慜偵丒丒丒乿偲偄偆偙偲傕帺慠偵峴側偭偰偄傞婥偑偡傞丅偙傟偼暣傟
傕側偔嬥娗妝婍傪墘憈偟偰偄偨偲偒偵恎偵偮偗偨廗姷偱偁傞丅壧傪巕嫙偺崰偐
傜傗偭偰側偐偭偨偙偲傪夨傗傫偩偙偲傕偁偭偨偑丄崱偱偼傓偟傠嬥娗妝婍傪宱
尡偟偰偍偄偰椙偐偭偨偲巚偭偰偄傞丅
丂柺敀偄偙偲偵丄婍妝墘憈壠偼丄妝婍傪墘憈偟側偑傜摢偺拞偱壧偭偰偄傞傛偆
偱偁傞丅帪偵偼丄偦偺摢偺拞偺壧偑惡偵側偭偰弌偰偒偰偟傑偆傛偆偱丄僶僢僴
抏偒偱桳柤側僌儗儞丒僌乕儖僪偼巚偄偭偒傝俠俢偵旲塖偑擖偭偰偄傞偟丄侾侽
擭埲忋愄偵暦偒偵峴偭偨拠摴堣戙偝傫偺僺傾僲儕僒僀僞儖偱偼丄僺傾僯僗僩帺
傜媞惾偱傕暦偙偊傞偔傜偄戝偒側惡偱庡慁棩傪僴儈儞僌偟偰偄偨丅傑偨丄僕儍
僘僩儔儞儁僢僞乕偺擔栰岍惓偝傫偼丄掜巕傪庢傞偲偒偵丄嵟弶偵乽偙偺慁棩傪
壧偭偰壓偝偄乿偲帋尡傪偡傞偦偆偱偁傞丅斵濰偔丄乽壧偊側偄傕偺傪妝婍偱墘
憈弌棃傞傢偗偑側偄乿偦偆偱偁傞丅
丂彮乆嫮堷側榖偺帩偭偰峴偒曽偱偼偁傞偑丄杔偼乽壧乿偼慡偰偺壒妝偺拞妀偵
埵抲偡傞傕偺偩偲巚偭偰偄傞丅嵟傕娙扨偱丄嵟傕擄偟偄壒妝偺昞尰庤抜丅偦傟
偑丄乽壧乿側偺偱偼側偄偩傠偆偐丠
|
仾儁乕僕偺愭摢傊
|
仧 2003擭06寧05擔(栘)丂敿壒偺鏰乮偒偟乯傒
|
丂愭擔丄尰嵼孮攏偱崌彞傪懕偗偰偄傞戝妛帪戙偺桭恖偺強懏偟偰偄傞崌彞抍偺
墘憈夛傪暦偒偵丄梱乆孮攏導嬍懞挰傑偱峴偭偰偒偨丅偦偺拞偺墘栚偵丄僀僞儕
傾偺僶儘僢僋帪戙偺嶌嬋壠儘僢僥傿乮Lotti c1667-1740乯偺 "Crucifixus"
乮廫帤壦偵偮偗傜傟乯偲偄偆崿惡俉晹偺嬋偑偁偭偨丅偙偺嬋偼丄慡曇傪捠偠偰
奺僷乕僩娫偺敿壒偺傇偮偐傝偑昿弌偟丄僉儕僗僩偺狩乮偼傝偮偗乯偺捝傒傪敿
壒偺鏰傒偵傛偭偰昞尰偟偰偄偰偄傞丅偦偺嬋偺揥奐偺柇偑丄屄恖揑偵偲偰傕岲
偒偱丄枅擔偺傛偆偵偙偺嬋偺墘憈俠俢傪挳偄偰偄偨帪婜偑偁偭偨丅
丂偳偆傗傜丄杔偼乽敿壒偺傇偮偐傝乿偑岲偒側傛偆偱偁傞丅婥偵擖傞嬋偵偼丄
昁偢侾夞偼偙偺傇偮偐傝偑弌偰偔傞丅
丂偝偰丄偙偙偱僴僗儔乕乮Hassler 1564-1612乯偺儌僥僢僩 "Dixit Maria" 傪
尒偰傒傞丅弌偩偟偺僥僲乕儖偺慁棩偵傾儖僩偑壛傢傝丄偡偖偵乮屌掕僪偱乯僪
偲僔偺乽敿壒偺傇偮偐傝乿偑尰傟傞丅偙偺傛偆側娭學偑懠偺僷乕僩偱傕師乆偲
尰傟丄嵟弶偺堦儁乕僕撪偱偞偭偲悢偊偨偩偗偱傕嵟掅俉売強偼乽敿壒偺傇偮偐
傝乿傪尒偮偗傞偙偲偑弌棃傞丅偙偺悢偼丄偙偺帪戙偺嶌昳偲偟偰偼堎椺偺懡偝
偱偁傞丅
丂偦偙偱丄偦偺傛偆側乽敿壒偺傇偮偐傝乿偺懡偄嬋乮夁嫀偱偼僾乕儔儞僋側偳乯
傪傾儞僒儞僽儖偡傞嵺偵僥僋僯僢僋偲偟偰昁梫偵側傞崁栚傪嫇偘傞偲丄
乮侾乯惓妋側壒掱偱丄
乮俀乯傇偮偐傞憡庤偐傜摝偘偢丄
乮俁乯傇偮偐偭偰偄傞偙偲傪堄幆偡傞偙偲
偱偁傞丅偙偺俁偮偺偙偲偑幚尰弌棃傟偽昁偢丄
乮係乯傇偮偐傝偭偰妝偟偄両
偲偄偆偙偲偵側傝丄偦偺寢壥椙偄墘憈偑惗傑傟傞偺偱偼側偄偐偲巚偆丅
丂崱偺抍偺恖悢丄峔惉偵偲偰傕儅僢僠偟偰偄傞偲巚偊傞偙偺僴僗儔乕偺嬋偨偪丄
嵟廔揑偵偳偺傛偆側壒妝偵側傞偺偐偑丄崱偐傜偲偰傕妝偟傒偱偁傞丅
|
仾儁乕僕偺愭摢傊
|
仧 2003擭05寧26擔(寧)丂巕壒偺張棟偵偮偄偰
|
丂廡枛偵擇偮偺墘憈夛偵峴偭偰偒偨丅堦偮偼戝恖悢偺抝惡崌彞抍偺掕婜墘憈夛丄
傕偆堦偮偼斾妑揑偵恖悢偺彮側偄怓乆側崌彞抍乮彈惡偍傛傃崿惡乯偑擖傟戙傢
傝棫偪曄傢傝壧偆偲偄偆僀儀儞僩偱偁偭偨丅偙偙偱偼丄慜幰偺抝惡崌彞抍乮俲乯
偲屻幰偺僀儀儞僩偱旕忢偵報徾偵巆偭偨彮恖悢偺崿惡崌彞抍乮俼乯偲偺斾妑偐
傜丄敊慠偲峫偊偨偙偲傪彂偄偰傒傞丅
丂偙偺俲偲俼傪扨弮偵摨偠搚昒偺忋偵忋偘傞偺偼丄傕偟偐偟偨傜娫堘偄偐傕偟
傟側偄偑丄偦偺斾妑偐傜峫嶡偟偨偙偲側偺偱丄巇曽偑側偄丅偙偺擇偮偺抍懱傪
暦偄偰丄柧傜偐偵堘偭偨偺偼丄乽墘憈偺拞偵棳傟傞嬞挘姶乿偱偁偭偨丅偦偺棟
桼偼怓乆偲偁傞偲巚偆偑丄偦偺堦偮偵巕壒偺張棟偺偟曽偑偁傞偲巚偆丅摿偵丄
俼偑壧偭偨僶僢僴偼丄僉儗偑偲偰傕傛偔丄偳傫偳傫墘憈偵堷偒崬傑傟偰峴偭偨丅
椺偊偑壓庤偩偑丄巜婗幰偺巜婗朹偵傄偭偨傝偲壒偑挘傝偮偒丄偁偨偐傕巜婗朹
偺愭偐傜壒偑敪偟偰偄傞傛偆側報徾偩偭偨丅堦曽偱丄俲偵偮偄偰偼丄擔杮岅丄
儔僥儞岅偄偢傟偵偍偄偰傕丄摿偵壒偺棫偪忋偑傝偺晹暘偵慹嶨偝傪姶偠偨丅偦
偺寢壥丄嬞挘姶偼偍傠偐丄擔杮岅偺壧帉偡傜帹偵撏偐側偐偭偨丅
丂偙偙偱尵偭偰偄傞偺偼丄乽彮恖悢枩嵨両乿偲偄偆偙偲偱偼側偄丅壖偵俲偑丄
乮戝恖悢側偺偱擄偟偄偲偼巚偆偑乯巕壒傪僺僞儕傪崌傢偣偰偔傟偽丄偦傟偼彮
恖悢偺抍懱偺壗廫攞傕姶柫傪庴偗偨偙偲偩傠偆丅幚嵺丄慺惏傜偟偄戝恖悢抝惡
崌彞偺墘憈傪偙傟傑偱偵婔搙傕暦偄偰偒偨丅
丂偙偺偙偲偐傜丄乽巕壒傪偒偪傫偲張棟偡傞乿偲偄偆偙偲偵僄僱儖僊乕傪拲偖
偙偲偵傛傝丄偦偺墘憈偵偼乽嬞挘姶乿偑惗傑傟傞偺偱偼側偄偐丠偲峫偊偨傢偗
偱偁傞丅
丂偝偰丄崱楙廗偟偰偄傞僴僗儔乕偺嬋偺 "Gloria" 偺拞偵丄
丒Qui tollis peccata mundi
偲偄偆壧帉偑偁傞丄偙偺 "Qui"乮懡暘塸岅偺 "quiz" 偺 "qui-" 偲摨偠敪壒乯
偼敪壒婰崋偱彂偔偲 [kwi] 偱偁傞丅壧偼婎杮揑偵攺偺摢偼曣壒偱偁傞偨傔丄
[kw] 傑偱偑巕壒偲峫偊傞偲丄偙偺 [kw] 偼攺偺愭摢傛傝傕愭偵敪偣傜傟側偗
傟偽側傜側偄偼偢偱偁傞丅挿擭丄壗偲側偔廃傝偵崌傢偣偰偙偺 "qui" 傪張棟
偟偰棃偨偺偩偑丄嵟嬤偙偺偙偲偵婥晅偒丄栚偐傜僂儘僐偑億儘億儘偲棊偪偨丅
丂慜夞偺曅栰愭惗偺楙廗偱偼丄帪偵岅旜偺 "-s" 偵偮偄偰揙掙揑偵拲堄偝傟偨
偑丄岅旜摨條丄岅摢乮摿偵擇廳巕壒丗"Gloria", "Christe", "Gratias" 側偳乯
偵傕嵶怱偺拲堄傪暐偄偨偄傕偺偱偁傞丅
|
仾儁乕僕偺愭摢傊
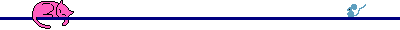

![]()