【注1】
二重母音は上で紹介したほかにも
《EI》 《EU》 《UI》 の3つがありますが、
ほとんど出てこないので、ここでは省略しました。
読み方は 《AU》 と同様です。
なお「Deus」などに出てくる 《EU》 の綴りや
「eleison」の 《EI》 の綴りは、
二重母音ではなく、2つの母音が並んでいるだけです。
【注2】
実のところ、ラテン語で「I」と「J」とは同じ字です。
その昔、ラテン語には「I」という字しかなく、置かれた場所によって
母音になったり子音になったりしていました。
それが時代を経るにつれて、子音化した「I」を
「J」と書くようになったのです。
ですので例えば、「Jesus」「cujus」「Jerusalem」などのように
「I/J」を分けて書く場合と、
「Iesus」「cuius」「Ierusalem」のように
一貫して「I」を使う場合とがあります。
(ちなみに私が訳すときは、すべて「I」に統一します)
【注3】
唯一の例外としては、接続詞「cum」の変化した
「quum」(発音は「ku-um」)という単語がありますが、
めったに出てきません。
【注4】
「軽く」濁る、と書いたのには理由があります。
もともと、Sはどれも清音で発音していましたが、
時代が下るにつれて「母音間のSはすこし濁る」と
いうように変化していきました。
おそらく、Sが前後の母音(有声音)と同化作用をおこして
結果わずかに有声化されるからだろうと思います。
手元の資料を見ると、
「S−二個の母音の間にある場合には、少し濁る。しかし決してフランス語のZほどは濁らない」
テ・ラローシュ『ソレム楽派によるグレゴリオ聖歌の歌い方』岳野慶作訳(音楽之友社,1990),29頁
「S………《母音間で》は軽く和らげられる」
水島良雄『グレゴリオ聖歌』(音楽之友社,1966),72頁
どちらにも「軽く濁る」という意味のことが書かれてますので、
傍証にはなると思います。
なお、難しければ清音でもいい、というのは私の拡大解釈です。
上述の理由から、有声化は結果として起こるものであり、
意図的になされるものではない、と考えてこのように書きました。
ただしこれは適切な資料にもとづく発言ではありません。
というより現時点で、いわゆる「標準発音」を規定した一次資料を
私は残念ながら知りません。逆に、たとえば水島・前掲書では
Sの清音化がはっきり否定されていますが(72頁注)、
これの論拠となる資料も明示されていないので
何故いけないのかという理由はよくわかりません。
【注5】
この理由は端的にいって、曲数があまりに違うからです。
有名な作曲家の作品だけでも:
Ave Maria…ジョスカン、パレストリーナ、ビクトリア、
アルカデルト、バッハ=グノー、ブルックナー、
ラフマニノフ(翻訳)、ブラームス、ホルスト、
コダーイ、ストラヴィンスキー、ほか多数
Salve Regina…オケゲム、ジョスカン、プーランク、
ペルト、オルバーン、コチャール、ほか現代作曲家に多数
こんなにあります。なのに「Alma Redemptoris」は(私が知る限り)
ブストに1曲ある他は全く知られていないようです
(それだって相当マイナーです。合唱譜のカタログを調べてみても、
他にはMiškinisというリトアニア人の曲ぐらい)。
なぜこんなに差が。。。
【注6】
「qui」の母音「I」は、実際には短い母音です。
本文では、母音を強調するために「イー」と
のばして書いただけで、長い母音ではありません。
【注7】
大したことじゃないんですが一言。
この「つながる」現象のことを、合唱の人たちの間では俗に「リエゾン」
とか言ってますが、この呼び方はじつは間違いです。
リエゾン(liaison、連音)はフランス語の文法用語で、
本来発音
されない語末の子音が、
続く単語の頭にある母音とつながって発音
されるようになる
現象のことをいいます(定義は「2母音間に支えの子音を挿入すること」)。
例:vous‿avez / les‿enfants / un grand‿hotel
もともと発音される語末の子音がすぐ後の母音とつながる場合、
フランス語ではアンシェヌマン(enchaînement)と呼んで区別します。
ほかの言語での似たような現象はlinkingなどと呼びます。
まあ何と呼ぼうが自由といえばそうなのですが、カタカナ語をむやみに使うのが、
どうも安っぽくて好きになれないので書きました。
【注8】
細かく言えば、音節を強調する際には、
音を高くするのと強くするのと2つやり方があって、
それぞれ
ピッチ(高低)アクセント、ストレス(強勢)アクセントといいます。
日本語はピッチアクセントですが、これは
「理屈の上では、音の強弱をつけなくても高低だけでアクセントが通じる」
ことを意味します。実際に喋るときは往々、強弱をともなっています。
ラテン語は英語、ドイツ語などと同様にストレスアクセントです。
【注9】
辞書を引けば、全ての単語について母音の長短が載っています。
母音の上に 「―」(横棒)があれば長母音、
上に何も書いてない、または「∪」(丸括弧を倒したみたいなの)
があれば短母音です。
辞書は、大きめの市立図書館に行けば、たぶんあります。
大学の図書館にも必ずあります。(中学や高校だと、残念ながらまず置いてません)
お金に余裕があれば、思い切って買うのも悪くないです。
かなり大きい本屋でないと扱ってませんが、Amazonに行けば一発でしょう。
おすすめは特にない、というかあまり知らないのですが、私が使っているのは
D. P. Simpson,
Cassell's Latin Dictionary (Macmillan, 1959)
です。私の西洋古典の先生がすすめてくれたので、それをそのまま買いました。
要領よく意味がまとまってて、まあまあ使いやすいです。
大きさもA4より一回り小さいくらいで手頃だし。
でも高い。買った当時で約5000円。値札見て、鼻血出そうでした。
【注10】
解答は次の通りです。
1.sacramentum=「MEN」
2.requiescat=「ES」
3.benedictus=「DIC」
4.ascendit=「(S)CEN」
の位置にそれぞれアクセントが来ます。
【注11】
ちなみにこの例(genitrix)では、「NI」のIが短母音なので、
アクセントは「GE」です。
【注12】
くちのふた、と書いて口蓋(こうがい)。
口の上天井のことです。
もっと細かく分けますと、まず、上の前歯の裏側は歯茎ですね。
そこから少し後ろに下がると、かくんと傾斜が急になるところがあります。
だいたいこの曲がり始めあたりから後ろが
硬口蓋(こうこうがい)。
さらに下がっていくと、硬かった天井があるところから軟らかくなります。
この軟らかい部分(から後ろ)が
軟口蓋(なんこうがい)、と
それぞれ名前がついています。
【注13】
なぜ「ラテン語の発音」といわないか、というと、
ローマ人はもういないし、現在使われていない言葉なので
元々どういう発音だったかが正確には分からないからです。
ですから実際のところは、ラテン語の発音というのは
現代ヨーロッパ語の発音をもとに決めているわけでして
これが唯一正しい、とはなかなか言いにくい。
教会ラテン語はイタリア語の発音がベースなので
子音のポジションも基本的にはイタリア語のものを参考にするわけですが、
他の近い言語、たとえば英語の発音なんかも
似ているものは参考にして構わないだろう、ということです。
【注14】
L音は、よく
流音(りゅうおん)とも呼ばれますが、
これはかなり耳の印象に頼った呼び名です。
流音というときには、しばしばRを含めてこう呼ばれ、
たまにMやNまで含まれます。
英語の流音はLだけ、ラテン語やフランス語ではL・Rの2種、など
言語によっても含まれる子音が異なってきます。
文法の世界ではよく使われますが、音声学的な根拠はむしろ薄い言葉で
少なくとも、発音を解剖的に分析してみる場合には
全然役に立たない呼称です。
歌うためのラテン語入門 by かずのみや
©Kazunomiya since 2004, All Rights Reserved.
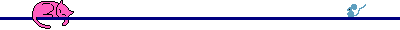
![]()