�ǂ{
�ړ��̓d�Ԃ̒��ȊO�ł͂قƂ�ǓǏ������Ȃ��̂Ńy�[�X���x���ł����A
�ڂ��̓ǂ{�𐔍s�R�����g��Y���ė�L���čs���܂��B
�i2009�N4��25���J�݁j

2025�N
-
�w����s�x�i���F����\��j�m�W�p�Е��Ɂn NEW!!
�v���Ԃ�̒��ҏ������������A����\��炵���O�������Ȃ��X�g�[���[�̃e���|�œǂݐ邱�Ƃ��o�����B
�i�X�\����Ă���M���������^���Ƀh�L�h�L���Ȃ�����A�ŏI�I�ɋ~�����Ȃ��ِF�̍�i�B
�q���̎��̕s�K�ȑ̌����A�����܂ŋ��낵���l�Ԃ����グ��Ƃ́B�s���̖��삾�Ǝv���B
�i2025�N8��13���Ǘ��j
-
�w�ˉB�`���E�l�����x�i���F���c�N�v�j�m�p�앶�Ɂn
�w���҂̖ؗ�x�ɑ����ē��c�N�v��i��ǂ�ł݂����A�v���̊O�ʔ��������B�i1983�N7�����s�j
�����ꂽ���オ����Ȃ̂ō��ǂނƈ�a���͂��邪�A���̎��㐶�����҂Ƃ��Ă͉������������o�����B
���ۂɌˉB�ɓ`���S���g�t�`�������~���ɂ�����z�V�O�ȓW�J�ɁA�ő���ۂނ��Ƃ����B
�i2025�N6��4���Ǘ��j
-
�w�Z�ҍH��x�i�W�p�Е��ɕҏW�� �ҁj�m�W�p�Е��Ɂn
��N�ǂw�Z�ҕ����x�ƈꏏ��Amazon�Ń|�`�����F�X�ȍ�Ɓi12�l�j�̖���Z�ҏW�B
�D���ȍ�Ƃ̍�i�����߂��Ă��Ă�����������A�ǂ��Ƃ̂Ȃ���Ƃ̊J��ɂ��𗧂����B
�ɍ�K���Y�́w���z�̃V�[���x�͈ȑO�ǂ��Ƃ����������A��͂薼�삾�Ǝv�����B
�i2025�N4��11���Ǘ��j

2024�N
-
�w���҂̖ؗ�x�i���F���c�N�v�j�m�p�앶�Ɂn
BS��OA���Ă����w�M�Z�̃R�����{�V���[�Y�x�����܂��܌��āA�ʔ��������̂œǂ�Ō������Ȃ����B
1981�N�̒��҂ɂ�鎩��o�ł�����t���������ŁA�����I�ȃx�X�g�Z���[��Ƃ̃f�r���[��B
���ۂɔѓc�ŋN�����o���o���E�l�������x�[�X�ɁA��҂̃C�}�W�l�[�V�����Ŗc�����B
�i2024�N12��28���Ǘ��j
-
�w�Z�ҕ����x�i�W�p�Е��ɕҏW�� �ҁj�m�W�p�Е��Ɂn
�R���i�Ђł�������{��ǂ܂Ȃ��Ȃ����̂ŁA�Z�҂�������C�P�邩���Ǝv���w���B
16�l�̍�Ƃ̒Z�ҏ������P���ɂ܂Ƃ߂����������Ƃ����̒Z�ҏW�ŁA�������B
�������i�A�����i�A�O������i�A��ۂɂ��܂ł��c���i�A�A�A��������҂�ǂޗ\��
�i2024�N10��30���Ǘ��j
-
�w���A��o�R�̃X�X���@�������A�R�֍s�����I�x�i���F��݂��j�m�u�k�Е��Ɂn
�R���i�Јȍ~�R�o��ɍs���Ă��Ȃ����A�ȑO�̂悤�ɓ��A��ōs����͈͂̒�R�ɓo���Ă݂����Ǝv���Ă��āA
�ĊJ�Ɍ����ă��`�x�[�V�����������ł��グ�鏕���ɂ��Ȃ邩�Ɠǂ�ł݂��B�����������̖��悪�ʔ����B
�s�������Ƃ̂���R�[�X���ڂ��Ă��肵�ă��N���N�����̂ŁA���H���炢�ɋv���Ԃ�ɍĂэs���Ă݂悤���ȁH
�i2024�N8��6���Ǘ��j

2023�N
-
�w���̖��Ƃ��x�i���F��㖢�f�q�j�m�u�k�Е��Ɂn
�f��u�A�C�X�N���[���t�B�[�o�[�v���A���̒Z�ҏW�Ɏ��^����Ă���u�A�C�X�N���[���M�v��
���ĂɂȂ��Ă���Ƃ������ƂŁA�ǂ�ł݂����Ȃ�B���ۂɂ͉f��Ƃ͈Ⴄ�X�g�[���[���ۂ��B
�S�̓I�ɃV���[���ŁA�u���Ԕ����g�v�Ȃǂ́A���Ȃ�Ռ��I�Șb�������B��ǂނƂ�����ƕ|���B
�i2023�N9��3���Ǘ��j
-
�w���ɉj���`���R���[�g�O���~�[�x�i���F���c���̂��j�m�V�����Ɂn
�u�͂₭�N�������́E�E�E�v�i�t�W�e���r�j�ŁA���M���q���Љ�Ă����A��Z�ҏW�B
���X�����V�[���������ɏo�ė��邪�A�ŏI�I�ɂ̓n�[�g�E�H�[�~���O�ɂȂ��Ă��ăz�b�Ƃ���B
�����ڐ��̓��e�Ƃ����̂����邪�A����ł͑̌��o���Ȃ����ƂŊ����邱�Ƃ��o����G��B
�i2023�N2��2���Ǘ��j

2022�N
-
�w���E�̏I���ɎČ��ƂS�x�i���F�Ό� �Y�j�mKADOKAWA���f�B�A�t�@�N�g���[�n
��Q�N�O�ɑ�R����ǂ�ł��āA�ŐV���̑�S�����w���B�����Ƒ����Ăق�����i�̈�B
��l�i���j���̃n����A��Ă̖k�C���`���k�`�V���̗��B�e�n�̖������o�ꂵ�ʔ����B
�ŏI�b�̒��ҁw���u���^�[�x�́A�y�b�g�����������Ƃ�����l�Ȃ�K��������b�B
�i2022�N12��27���Ǘ��j
-
�w��ǔL�h�������x�i���F�䑺 �O�j�m�u�k�Е��Ɂn
�v���Ԃ�ɕ䑺����̃G�b�Z�C���ǂ�ł݂����Ȃ�A�l�b�g�Ń|�`���B�S���a�ށB
���X�k�C���V���ɘA�ڂ���Ă������̂炵���A�䂪��Z�̘b���o�ė��Ėʔ��������B
�N��̓M���M���d�Ȃ��Ă��Ȃ����A�w������ɉ��h�����ꏊ�����݂����߂��Đe�ߊ��{���B
�i2022�N11��26���Ǘ��j
-
�w�V��ƃs�A�m�x�i���F��_���ݎq�j�m�|�v���Ёn
�l�b�g�ł��܂��܌����āA�ʔ������Ȃ̂ōw���B50�Α�Ŏv�������ăs�A�m�ɑł����ޘb�B
���҂������N�Ƃ������Ƃ�����A�V����ǂ̂悤�ɉ߂��������l����������B
�S�̂Ɋy�����G�b�Z�C��i�ł͂��邪�A���Ɍ㔼�͂��̍����炱�������郁�b�Z�[�W�����ځB
�i2022�N4��9���Ǘ��j

2021�N
-
�w�C�F�̚ށx�i���F�c�ۉ�q�j�m�o�t���Ɂn
�O��́w�����x�ƈꏏ�ɍw�����A�Y�ꂽ���Ɉ�b�ǂނ悤�ȃy�[�X�ł���ƓǂݏI�����{�B
�N�Z�̂����i���������A�w�n�^�Ƌ��x���n�^�̐l�ԂƂ��Ă͂ƂĂ��ʔ��������B
�ŏI�b�́w�C���x�́A��\��ƌ����邾���̂��Ƃ����āA�m�X�^���W�b�N�ȏG�삾�Ǝv�����B
�i2021�N8��10���Ǘ��j
-
�w�����x�i���F�c�ۉ�q�j�m�o�t���Ɂn
���܂��ܒ��҂̑Βk���e���r�Ō��āA������Ɠǂ�ł݂悤���Ǝv���|�`�b�Ă݂��B
�V���[�g�V���[�g��ǂނ̂͐��V��ȗ����H�S�̓I�ɂ��̃W���������L�̃V���[���A�u���b�N��
��i���Ȃ��͂Ȃ����A�ŏI�b�́w�����x�̂悤�ȃz�����Ƃ����鉷���݂��������i���������^�B
�i2021�N1��20���Ǘ��j

2020�N
-
�w���E�̏I���ɎČ��ƂR�x�i���F�Ό� �Y�j�mKADOKAWA���f�B�A�t�@�N�g���[�n
��P�N�O�ɑ�Q����ǂ�ŁA�҂��ɑ҂�����R�����w���B�^�ʔ̃T�C�g�Ő�s�\��B
��l�i���j���̃n���̔��������N�w�I�ɂȂ��ė��Ă��Ė������������Ă���B
�ŏI�b�̒��ҁw�Ă̏I���ő҂N�Ɓx�͏d���e�[�}�B�܂Ȃ��ł͓ǂ߂Ȃ��B
�i2020�N12��31���Ǘ��j
-
�w�A�C�l�N���C�l�i�n�g���W�[�N�x�i���F�ɍ�K���Y�j�m���~�ɕ��Ɂn
�ē��a�`�̃A���o���u�g�Ձv�̈�Ȗځu�A�C�l�N���C�l�v�Ƃ̃^�C�A�b�v�Z�ҏ�������
���W�����ِF�̘A��Z�ҏW�B�l�ԊW�̃����[���ʔ����̂����A�ꃖ���ȏォ���ēǂ��߁A
���ǓǗ�������ɑS�̂�������x�����ƓǂݕԂ��H�ڂɁB���������{�͐����ň�C�ɓǂނɌ���B
�i2020�N12��29���Ǘ��j
-
�w�`���h�����x�i���F�ɍ�K���Y�j�m�u�k�Е��Ɂn
�O��́w�T�u�}�����x�̑O�삾�������Ƃ��킩��A���ۂɂ͐ϓǂ������̂œǂ�ł݂�B
�o��l�����d�Ȃ��Ă��ĒZ�ҏW�ɂ�������炸�A�u�ߋ��ƍ������҂���ِF�̍\���v�i������j
�Ƃ����̂��ƂĂ��ʔ��������B���ꂩ��̂��̍�Ƃɂ��x���ꑱ����̂��낤�Ȃ��B
�i2020�N9��18���Ǘ��j
-
�w�T�u�}�����x�i���F�ɍ�K���Y�j�m�u�k�Е��Ɂn
�A��Z�ҏW�w�`���h�����x�̑��҂炵���B�w�`���h�����x��ǂ�ł����C�ł��������ǁB
�{�I�ɂ͂������̂ŋt�]�œǂ�ł݂悤�Ǝv���B�����͑��ς�炸�U���U�����Ă��邪�A
���ʓI�ɐl���Ď̂Ă�����Ȃ��Ȃ��Ƃ������X�g�ɂȂ����čs���C�����̗ǂ���i�B
�i2020�N8��17���Ǘ��j
-
�w�r�ƍ|�̐X�x�i���F�{���ޓs�j�m���t���Ɂn
2016�N�ɑ�13��{����܂Ȃǐ��X�̎�܂������b���B�y�x�z�̒��ԂɎ�ēǂށB
�Ⴂ�����t�̐�����`������i�����A�}�j�A�b�N�ȕ����ɑ���߂��邱�ƂȂ��A
���y��������l�����B���X�g�̑o�q�̎o���Ǝ�l���̂��Ƃ肪�����I�ŁA���S���M���Ȃ�B
�i2020�N4��15���Ǘ��j

2019�N
-
�w���E�̏I���ɎČ��ƂQ�x�i���F�Ό� �Y�j�mKADOKAWA���f�B�A�t�@�N�g���[�n
�R���ɑ�P����ǂ�ŁA�҂��ɑ҂�����Q�����w���B�^�ʔ̃T�C�g�Ő�s�\��B
���e�A�G�Ƃ��N�I���e�B�[������w�A�b�v���������ŁA���x���ǂݕԂ������Ȃ�B
��l�i���j���̃n���̔����錾�t�ɂ��������������āA���X�z�����Ƃ�������B
�i2019�N11��26���Ǘ��j
-
�w���E�̏I���ɎČ��Ɓx�i���F�Ό� �Y�j�mKADOKAWA���f�B�A�t�@�N�g���[�n
�y�x�z�̉̂̒��Ԃ���c�C�b�^�[�ŘA�ڂ���Ă���Ƃ����̂��Ĉꕔ�������Ă�������B
�Č��D���Ƃ��ẮA���̕\��A���������킢���āA�����ǂݐi��ł��܂��B
��l�i���j���̃n���̔�����̂��N�w�I�Ȕ����ŁA�����l���Ȃ���킩��Ȃ������肷��B
�i2019�N3��22���Ǘ��j
-
�w�I���e�K ��O�̔��t�@�����Ƃ����u遂�v�x�i���F�����x�u�j�mNHK 100��de�����n
���܂��ܖ钆��E�e���ōĕ��������Ėʔ����Ǝv���A�e�L�X�g���Ă݂��B
�ێ�Ƃ̓��x�����Ƃ͂Ȃǐ^�ʖڂɍl�������Ƃ��Ȃ������̂ŁA���ɂȂ����B
�u�ߋ��̉p�m�ƂƂ��ɐ�����v���Ƃ̏d�v�������߂Ċ����邱�Ƃ��o�����B
�i2019�N3��18���Ǘ��j

2018�N
-
�w�ɂ�ɂ�ɂ���L�x�i���F�䑺 �O�j�m���t���Ɂn
�y�k�z�̉̂̒��Ԃ���̐l�ł����邱�̒��҂��Љ��Ĕ����Ă݂��B
���L���̃G�b�Z�C�̌������Z�̂̌y�������m�������킹�Ă��ʔ����B
�^�C�g���u12��14�� �ӓ����v�������I�Ɉ�ԃE�P���B�ʋΓd�Ԃł͊댯�Ȗ{�B
�i2018�N8��26���Ǘ��j
-
�w������A�������@�`���ƂȂ������ā`�x�i���F�� �^���q�j�m�u�k�Е��Ɂn
���������̂����Y��Ă��܂������A�{�I�ɖ��ǂŗ����Ă����{����Ɏ��B
���肩����z���o����悤�ɁA������s�ς̓����Ҏ��_�̒Z�ҏW�B
���e�͂܂�����Ȃ��Ǝv�������A���߂ēǂ��̒��҂̕��͂̔���������ۂɎc�����B
�i2018�N7��18���Ǘ��j
-
�w�\�������̋U�i�P���`�U���j�x�i���F�{���݂䂫�j�m�V�����Ɂn
��T���u�����v�A��U���u���Ӂv�A��V���u�@��v�̂Q���ÂR���ɕ������咷�ҁB
�����V���ɂP�O�N�ԘA�ڂ���Ă����Ƃ������Ƃ�����A���̒����ɋ��������B
�o�u�����̈�̎�����ǂ���҂̎��_���A���̎�����������Ƀ��A���ɓ`����ė����B
�i2018�N6��7���Ǘ��j

2017�N
-
�w�������S���x�i���F�d�� ���j�m�u�k�Е��Ɂn
2015�N�Ƀh���}������Ă����͉̂��ƂȂ��L�������邪�A���R�ςĂ��Ȃ��B
���Ƒ��q�̊W���^�C���X���b�v�Ƃ���SF�^�b�`�̃X�g�[���[�Ō����Ă��Ėʔ����B
���X�g�V�[���̂�����Ǝ�O�̕��q�̂����Ńz�����Ƃ��Ă��܂����B
�i2017�N9��18���Ǘ��j
-
�w�����̂���Â߁x�i���F������������j�m�W�p�Е��Ɂn
1991,2�N�̍��́A������̉Ƃ̖{�I�ɒP�s�{�����Ȃ�̊m���œ����Ă����x�X�g�Z���[�B
�{���ŏW�p�Е��ɂ̕��ɖ{�t�F�A�u�i�c�C�`�v�ŕ��ς݂���Ă��āA���������Ŏ�Ɏ�����B
���ǂ�ł����킶��Ɨ���ʔ����́A�G�b�Z�C��i�Ƃ��Ē����ǂp����邱�Ƃ��낤�B
�i2017�N8��24���Ǘ��j
-
�w���Ɓx�i���F�d�� ���j�m�V�����Ɂn
���H����D�y�ւ̓d�Ԃ̎Ԓ��œǂނ��߂ɁA���H�w�̌Ö{���ōw���B�v���Ԃ�̏d����i�B
�u���Ɓv�Ɋւ��S�҂̒��ҏ����ō\���B�S�āu���v���e�[�}�ɂ��Ă��āA�S�ɋ����B
���ɂQ�Җڂ́u�������Α����v�͓��Ƀ��X�g�ŋ}�ɗ��Ă��܂��A�A��d�Ԃ̒��Ŋ��܁B
�i2017�N8��9���Ǘ��j
-
�w���ǂ̖l�����т͂˂闝�R�x�i���F���c�����j�m�p�앶�Ɂn
�m�g�j�̓��ԂŒ��҂̑��݂�m���āA�Ɛl���{���Łi���킹�đ������j�����ė����B
���̕a�̐l�������̐S�̓���������ƕ��͂œ`����Ƃ����̂́A���E�I�Ɍ��Ă��H�L�Ȗ{�B
�������������Ƃ��̔N�13�Ƃ����̂ɂ������B�����͂܂��������Ԃ�u���ēǂ����B
�i2017�N7��24���Ǘ��j
-
�w�k����w�b��w���@�����I�x�i���F�Ж�䂩�j�m�|�v�����Ɂn
�k����w�̏b��w��������X���̏\�a�c�L�����p�X�Ŏ��ۂɐݗ����ꂽ�T�[�N���u�����v�̎��b�B
��l�̊w���̔M�ӂ���n�܂������A�L�𒆐S�Ƃ����������슈���B���ł������Ă���Ƃ������琦���B
�����ď����Ɋ����o���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�l�X�ȍ�������z����w�������̎p�Ɋ��������B
�i2017�N6��30���Ǘ��j
-
�w�r�u���A�Ï��X�̎����蒟�V�@�`�x�q����ƉʂĂȂ�����`�x�i���F�O�� ���j�m���f�B�A���[�N�X���Ɂn
�u�r�u���A�`�v�����ɂV���ڂōŏI���B�U���̂��Ƃ����ɏ�����Ă����ʂ�̏I���B
����̓E�B���A���E�V�F�C�N�X�s�A�̌Ï��Ɠ䑽���B�m���͐��O�̞x�q����̊��ʔ��������B
�ꖺ�Ό��A�܉Y�ƞx�q����̊W�ȂǁA�ŏI�b�ɑ��������W�J�������B�V���[�Y���̂Ƃ��č��]���B
�i2017�N5��30���Ǘ��j
-
�w�c��S���o�P�[�V�����x�i���F�ɍ�K���Y�j�m�W�p�Е��Ɂn
��b�����ł���Ȃ���A�S�̂����ƂȂ��Ȃ����Ă��銴�������āA�ŏI�I�ɃI�`���t���B
�������������ȃX�g�[���[�W�J�́A���̍�Ƃ̓��ӂƂ���Ƃ���ŁA�l���C�ɓ����Ă���B
�o��l���̈����ׂ��L�����N�^�[���A������ƃV�r�A�Șb�����ǃR���f�B�ɂ��Ă��܂��Ă���B
�i2017�N4��16���Ǘ��j
-
�w���L���|�[�g�x�i���F�L�� �_�j�m�u�k���t�n
�v���Ԃ�̗L���i�ɁA���̃X�g�[���[�W�J�̏�肳�ɚX�炳���B��͂�e�N�j�V�������B
�e���ɖ���z�����Ƃ������A���܂�������40�N�Ԃ�̃N���X��ɎQ�����Ă����̂�������肱�߂��B
�Ō�̓W�J�́A����܂��S��I�Ƀ^�C�����[�߂��āA�f���ɓǗ�����Ɋ��z�����������Ɏ������B
�i2017�N3��28���Ǘ��j
-
�w�A���J�g���Y���z�i�㊪�E�����j�x�i���F���c���i�j�m���t���Ɂn
�ɍ�K���Y�����q����Ƃ�����Ƃ�2012�N�̍�i�B���߂ēǂ��A�S�̂̃X�g�[���[�̓W�J�������B
��i�̌㔼���⏑�ɂ��Ă��܂������Z���̎��ɓǂĖڟ��́w������x�ȗ��̏Ռ��B
�l�^��ɂȂ��Ă��܂��̂ŏڂ����͏����Ȃ����A�ŏI�I�ɂ͐F�X�Ȃ��Ƃ��ƂĂ��l�����������i�B
�i2017�N2��25���Ǘ��j

2016�N
-
�w�K�\���������x�i���F�ɍ�K���Y�j�m�������Ɂn
���Ɨp�ԁi�̃f�~�I���f�~�j�̎��_����A���̉Ƒ��ɋN���鎖����`�����ِF�~�X�e���[�B
�l�Ԃ����A��蕨���Ԃ̃L�����N�^�[���Z���āA�ʔ����āA���炵���B�G�s���[�O�͋������B
�����ԂƂ����l�Ԃ���̎g�ȗ���������������A��������E�͂��Ă��Ȃ��Ƃ��낪�▭�B
�i2016�N11��22���Ǘ��j
-
�w�킪������R�X�x�i���F�[�c�v��j�m���}�P�C���Ɂn
�w���{�S���R�x�̒��҂�1959�N�`1962�N�̎R�s�𒆐S�ɏ�����23�҂̋I�s�B
�푈���I����Ă܂�������o���Ă��Ȃ�����̎R���Ȃ̂ɁA�ÏL���������Ȃ��B
���҂̌������y���ŁA�����������s���Ă���悤�ȍ��o�������Ă��܂������B
�i2016�N9��28���Ǘ��j
-
�w��䂮�炵�x�i���F�ɍ�K���Y�j�m�W�p�Е��Ɂn
2005�`2015�N�ɏ������߂�ꂽ�G�b�Z�C�W�B���҂͐��ݏZ��ƂŁA�k�Ђ�����ł���B
�n���̎G���Ɍf�ڂ��ꂽ��i�W�Ƃ������ƂŁA���[�J���F�����Ղ�ŋt�ɖʔ����B
�k�Ќ�̐��̈ꐶ���҂̐S�̓������W�X�ƒԂ��Ă��āA���̉e���̑傫�������Ԃ�o���Ă���B
�i2016�N9��13���Ǘ��j
-
�w�y�e���̑���i�㊪�E�����j�x�i���F�{���݂䂫�j�m���t���Ɂn
�w�N���@Somebody�x�A�w�����Ȃ��Łx�ɑ����A�����V���[�Y��O��B�������ɓo��l�����g�߂Ɋ�����B
���C���̎����́A�㊪�ő��X�Ɋ������Ă��܂����A��������̐^���Ɍ����ẴA�v���[�`���ʔ����B
���X�g�ɁA��i�̃X�g�[���[�Ƃ͊W�Ȃ��������p�ӂ���Ă��āA�Ռ�����B����ւ̓W�J�̗\���B
�i2016�N8��16���Ǘ��j
-
�w���[�c�@���g�͉F���x�i���F�C�V�� �q�j�m���y�V�F�Ёn
���Ԃ�1991�N���ɔ������{�������Ɠǂ�łȂ��āA���X�Ȃ���ǂ�ł݂ĂƂĂ��ʔ��������B
���������[�c�@���g���Ɓi�I�^�N�j�̖v��200�N�̃������A���C���[�Ɍ����Ă̏������W�߂�����B
���̍�ȉƂ̒m��Ȃ������ʂ₻�̎���̔w�i�Ȃǂ̘b�����悢�܂Ƃ܂�̂Ȃ��ŎU��߂��Ă���B
�i2016�N6��28���Ǘ��j
-
�w�����Ȃ��Łx�i���F�{���݂䂫�j�m���t���Ɂn
�w�N���@Somebody�x�ɑ����A�����V���[�Y����B�傽��o��l���������Ȃ̂ŊȒP�ɓ����B
�{������炵���A�l�Ԃ̋��������i�����j��������Ȃ���A����ł��l���̂Ă�����Ȃ��Ƃ����b�B
�Ō�͂���Ӗ����̂ǂ�ł�Ԃ�������A�X�g�[���[�̃X�s�[�h�����f���炵�������B
�i2016�N6��13���Ǘ��j
-
�w�N���@Somebody�x�i���F�{���݂䂫�j�m���t���Ɂn
�{���̐V���R�[�i�[�Łw�y�e���̑���x�����ς݂���Ă���̂����āA�����V���[�Y��ǂݎn�߂�B
����̓���́A�������{���݂䂫�Ƃ��������B�v���Ԃ�̔ޏ��̍�i�͗���Ȃ������B
���킶��ƃX�g�[���[�ɓǎ҂���������ōs���Z�p�A���S�Șb���K���Ō�ɋ~���̂���W�J�͂������B
�i2016�N5��28���Ǘ��j
-
�w�W���C���X�R�[�v�x�i���F�ɍ�K���Y�j�m�V�����Ɂn
2006�`2013�N�ɎG���Ȃǂ̂��߂ɏ������Z��6��i�̍Ō�ɂɏ����낵��t����2015�N�̒Z�ҏW�B
���ꂼ��̘b�����ƂȂ��Ȃ����Ă��銴���������A�Ō�̘b�Œ��߂Ă����ʔ����\���B
��������������ɂ��ɍ�炵���āA�F�X�ȐF�������Ȃ���A�Ō�ŋ�������̂͂������B
�i2016�N5��5���Ǘ��j
-
�w�v�����Z�X�E�g���g�~�x�i���F����ڊw�j�m���t���Ɂn
�薼����\�z���Ă������e�Ƃ��Ȃ����Ă��āA�ǂ������ɗ���ꂽ�����B
���N�O�ɑ�����ӂ��ό����Ă����̂ŁA�y�n�������ƂȂ������Ċy���߂��B
�v�����Z�X�������̒j�����i���͏��������j�̐S�ӋC�Ƀz�����Ƃ�������銴����B
�i2016�N4��26���Ǘ��j
-
�w��������{�̓Y���Ă���x�i���F�Îs�����j�m�V���V���n
�������N�A�ԑg�̃R�����e�[�^�[�Ƃ��Ă��e���r�ɏo�Ă���Îs�����̏�����2014�N�̖{�B
�Љ�w�҂炵���A���̓��{�̎Љ��ے肵�Ȃ���A2040�N�̓��{�̎p��肤�B
���ꂩ�疢���Ɍ������̓��{��J���Ă��鍑���̈�l�Ƃ��āA�F�X�ƍl��������ꂽ�B
�i2016�N4��3���Ǘ��j
-
�w�ڂ����������S�E�X�g�x�i���F�ŊC���O�j�m�������Ɂn
�ɍ�K���Y�̃I�X�X���{�Ƃ������ƂŁA�Ɛl�������ė����{�B�ɍ�D�݂Ȃ̂��悭�킩���i�B
�r���܂Œ��ȃt�@���^�W�[���̂Ǝv���Ă������A���X�g�Ɍ������Ĉꖡ�����Ⴄ�����ɓW�J�B
���҂͌̐l�����A57���炢�̂Ƃ��̍�i�i2005�N���s�j�ƒm������B
�i2016�N3��20���Ǘ��j
-
�w�|���N���V�b�N�x�i���F����E��j�mNHK�o�ŐV���n
�ӂ���Ɗ�����{���Ŏh���I�Ȗ{�̑薼���C�ɂȂ��čw�������B�V���͈�����B
�e�N���V�b�N��i�̈�b���`��ɉ������Ă��āA�ǂ�ǂ�������܂�Ă�������B
�m���Ă������e�����������������A���߂Ēm���Ƃ��Ē~�ς��邱�Ƃ��o�����B
�i2016�N3��4���Ǘ��j
-
�w�l�͂����ɂ��Ďw���҂ɂȂ����̂��x�i���F���n �T�j�m�V��OH!���Ɂn
���ɉ��Ԃ��Ȃ����ɔ������͂�������A15�N���炢�O�ɔ������{�̍ēǁB
���␢�E�̍��n�ɂȂ������n�T�����34�̂Ƃ��ɏ������{�ŁA���ǂނƋt�ɖʔ����B
���j�[�i�o�[���X�^�C���j�Ƃ̍Ō�̕ʂ�̃V�[���Ȃǂ́A�܂Ȃ��ł͓ǂ߂Ȃ��B
�i2016�N2��8���Ǘ��j

2015�N
-
�w�Ɋy��̎�݂菗�x�i���F���c��j�j�m���ԕ��Ɂn
�Ɛl�������c���̍�Ƃ̍�i�����Ǝv���ĊԈ���Ĕ����Ă��܂����{�B
�M�C�̒��ŌJ��L������E�l��������芪���l�Ԗ͗l����A�Ɛl���Ď@��̎��_�Ő����B
�ǂ�ʼn��l�̂����i���ƌ�����ƁH�H�H�����A�Ɛl�͍��܂����̂ňӒn�ōŌ�܂œǂB
�i2015�N12��21���Ǘ��j
-
�w���y�̂܂����肢�x�i����V��@�R�{�e�q�j�m�}�����[�n
�́i����2000�N�ȑO�j�ɔ������{�ŁA�{�I�ɕ���ł���̂������ĂӂƍēǁB
����V��̏��������y�̋��ȏ��ɂ͏o�ė��Ȃ��}�j�A�b�N�ȍ�ȉƂ̐l���̃X�i�b�v�V���b�g�I�Ȃ��b�ƁA
���ʼn�Ƃ̎R�{�e�q�̍�i���D��Ȃ��R���{���[�V�����ɂ��A�s�v�c�ȓǂݕ��ɂȂ��Ă���B
�i2015�N12��17���Ǘ��j
-
�w�ӎ��́x�i���F�{�{�T��j�m�o�g�o�V���n
�����N���g�ł��Ԃ���̊���������{�{����肪���ތ�ɏ������{�B
�����ēV�˂ł͂Ȃ��������g�̖싅�ւ̎��g�݂��A�싅�ȊO�ɂ����Ă͂܂�ʔ����B
�v���싅�t�@���Ƃ��ẮA�I��̗��b�Ȃǂ��m�邱�Ƃ��o���Ĉ�C�ɓǂ߂��B
�i2015�N11��8���Ǘ��j
-
�w�����������܂イ�̐X�i�T���j�x�i���F�≪�q�T�G�j�mNemuki+�R�~�b�N�X�n
�S���܂ł͖��N�O�ɓǗ��B�T���Ŋ����B������҂̍�i���ł���ɂȂ��Ă���̂Ŋ������Ĉ��g�B
�o�ꂷ��L�����N�^�[���Z���̂ŁA��N�O�ɓǂ��e�������Ɗo���Ă����B
�߂����Ō�ł͂��������A�Ȃ����~��ꂽ���������ăz�����B�㖡�Ƃ��Ă͈����Ȃ��B
�i2015�N10��19���Ǘ��j
-
�w�W�����O�����i�㊪�E�����j�x�i���F��ˎ����j�m�w���m�[���R�~�b�N�XDELUXE�n
�{�I�ɒ������Ă����Ɛl�ۗL�̖���ɒ���B���̓A�j�������܂茩�����Ƃ��Ȃ��X�g�[���[�͖��m�B
�ӊO�ɂ����Ƀ��I�̂�������̃p���W�����E����Ă��܂��̂ɋ����B���̓��������̍s�����\�z�O�B
�߂��������Ɋ��܁B����ł����I�̈ӎu�̓��l�ւƈ����p����Ă������Ƃɋ~�����������B
�i2015�N9��21���Ǘ��j
-
�w��̍��̃N�[�p�[�x�i���F�ɍ�K���Y�j�m�n���������Ɂn
����w�I�[�f���{���̋F��x�Ɠ���������������t�@���^�W�[��i�B���̘H���͑����Ăق����B
�ɍ��i�炵���A�O���͏��Ȃ��������邪�A�㔼�̐���オ��Ɗ�z�V�O�̌����͂������B
���炩�ɋߌ���̎Љ�h���Ă��āA�n�b�ƋC�Â����Ă����Z���t�����ځB
�i2015�N8��18���Ǘ��j
-
�wBAR �������E�n�[�g�i�P���`�P�U���C�P�W���j�x�i���F�ÒJ�O�q�@�t�@�~���[����j�m�A�N�V�����E�R�~�b�N�X�n
�{�I�������ς��ɂȂ��ė����̂ŁA�������悤���Ƃ�����x�ǂݒ����B17���������Ă���̂͂����g�B
���C���ɖ��������ÂǂݕԂ������ɁA������Ă��܂��̂����������Ȃ��Ȃ�A���ǎc�����ƂɁB
�}�X�^�[�Ə��������ƃ��K�l����ƁA�����ɗ��邨�q����ŌJ��L������ق�킩�����b���ȂɂȂ�B
�i2015�N6��10���Ǘ��j
-
�w�A�h���t�ɍ����i�P���`�T���j�x�i���F��ˎ����j�m���t���Ƀr�W���A���Łn
�����O�ɍ����c�̒��Ԃ���Ђ����߂ė��w����Ƃ��ɏ���A�����ǂ����ƐϓǂɂȂ��Ă����{�B
���70�N��������Ƀ}�X�R�~�Ŏ��グ���Ă��鍡�����ǂނɒl�����i�ł���ƒɐɊ�����B
�X�g�[���[�͓��R�n��ł͂��邪�A���̎���̃��A���Ȑ���̓����������邱�Ƃ̏o����G��B
�i2015�N4��18���Ǘ��j
-
�w�ǐH���{�b�g�i�Q���j�x�i���F�≪�q�T�G�j�m�W�p�Ёn
2014�N6���ɓǂP���Ɏ����Q���B�f�ڂ��Ă����u�W�����v���v�̋x���ɂ��uCookies�v�Ɍf�ڈړ��B
�����O�H�Ƃ��R���r�j�H�Ƃ��ɑ����Ă��܂����̓��{�̖l�����ւ̌x���ɂ��ǂ߂�B
��͂莩���ō���ĐH�ׂ�̂���Ԃƍŋߎv���B�钆�ɓǂ�Ń|�e�g�T���_�������ɐH�ׂ����Ȃ����B
�i2015�N4��17���Ǘ��j
-
�w�O�C�̂������� �ӂ����сx�i���F�L�� �_�j�m�V�����Ɂn
�R�N�O�ɑO�т̕��ɉ��ɍ��킹�ĒP�s�{���o�Ă����̂͒m���Ă������ǁA�����Ɖ䖝���ĕ��ɉ��܂ő҂B
���ς�炸�̂��̍�Ƃ̃N�I���e�B�͍����܂ܕۂ���Ă��āA���ꂼ�G���^�[�e�C�������g�I
����͑�ܘb�̒�����̍Ղ�̘b�Ńz���b�Ɨ��Ă��܂��B�����Z�ނȂ炲�ߏ��Ƃ̊W�͑厖�B
�i2015�N4��1���Ǘ��j
-
�w�r�u���A�Ï��X�̎����蒟�U�@�`�x�q����Ə��邳���߁`�x�i���F�O�� ���j�m���f�B�A���[�N�X���Ɂn
�u�r�u���A�`�v�����ɂU���ځB���Ƃ����ɂ��A�������̎��̊��Łw�r�u���A�x�V���[�Y�͏I���炵���B
����͑��Ɉ�F�A�������w�ӔN�x���߂���l�X�Ȑl�Ԗ͗l���W�J�B���ɂ͍D���ȍ�Ƃ����ɖʔ����B
�������l�ԊW�����G�Ƃ������s�v�c�ȂȂ���Ƃ������E�E�E�������������Ȃ��B
�i2015�N3��13���Ǘ��j
-
�w���q�E�e�E�s��Y�m�ِF�Z�ҏW�n�i�P���`�S���j�x�i���F���q�E�e�E�s��Y�j�m���w�ٕ��Ɂn
�̂̒��Ԃɑ݂��Ă����{���A10�N�ȏ�Ԃ�Ɏ茳�ɕԂ��ė����̂ŁA�ēǂ����B
�u�h��������v���͂��߂Ƃ����q��������i�̍�҂Ƃ͎v���Ȃ��G�O���ƃO�����B
��҂̖{���ɕ`�����������E�́A���͂���ȕ��h�̌��������E�Ȃ̂��Ɖ��߂Ċ������B
�i2015�N2��17���Ǘ��j
-
�w�����т�ɉ̂��x�i���F���c�i��j�m���w�ٕ��Ɂn
2011�N�ɒP�s�{���o���Ƃ�����C�ɂ͂Ȃ��Ă������A�f�扻�ɔ������ɉ��ōw���B
�قڗ\�z���Ă����X�g�[���[�ł͂��������A�ӊO�ɂ�������Ƃ����e�C�X�g�ŗǂ������B
���w�E���Z����ɂ͍��������Ă��Ȃ������̂ŁAN�R���̋^���̌����o���Ėʔ��������B
�i2015�N2��19���Ǘ��j
-
�w�o�j�x�i���F�ɍ�K���Y�j�m�u�k�Е��Ɂn
�u�o�j�v�u���l�v�u���g�v�̎O�̕���́A��������ł���悤�łȂ��悤�Łc�b�͖ʔ����̂����B
�����̊����肪������̂Ɠǂݑ�����ƒɂ��ڂɍ����B�O�̓Ɨ��������ҏ����ƍl��������ǂ��B
���҂͂���܂łɂȂ��悤�ȍ\���̕�����������̂��낤���A�ǂ��ɂ��������������c��B
�i2015�N1��31���Ǘ��j
-
�w�v�`�˂��i�T���j�x�i���F�k�����K�j�m�A�t�^�k�[��KC �u�k�Ёn
�v���Ԃ�ɑ��҂�ǂ̂ŁA���炭���̐��E�ɓ���Ȃ��������A�㔼�y�[�X�����ށB
���ς�炸�L�̖��\��ȕ\��̕`��������肢�B���������A�L���Ă��������z�I
�S�R�}���̂ł́A�Z���t���Ȃ������ʔ��������肷��̂��s�v�c�Ȋ������B
�i2015�N1��5���Ǘ��j

2014�N
-
�w�m�낤�Ƃ��邱�ƁB�x�i���F���열�܁A����d���j�m�V�����Ɂn
�k�Ќ�Ƀc�C�b�^�[�Œm�荇������l�ɂ�錴�����̌�̂��ƂɊւ���Βk�B
�������i���Ƃ������Ƃ��͊W�Ȃ��A���̌㉽���N�����Ă��Ăǂ�������������B
�����͎����Ƃ��Č��X�^���X�ɍD�������Ă�B�̏K�������Ƃ�������Ǝv���o�����B
�i2014�N12��15���Ǘ��j
-
�w�Ȃ�Ђ���d�폤�X�i�Q���j�x�i���F�≪�q�T�G�j�m�C�u�j���OKC�n
�Q���������Ă��������Ƃ��������āA�������C���ɏ������ǂݐi�߂�B
�V������肽�����Ƃ���������l�����A�����Â������Ă����l�����܂����B
�ݒ�͋ߖ����̉����ł����Ă��A���̉����̓������Ղ�Ղ�Ƃ��낪�ʔ����B
�i2014�N12��11���Ǘ��j
-
�w���肬�肷�x�i���F���Ɏ��j�m�V�����Ɂn
�����ԑO�ɔ����Ė��ǂ̒Z�ҏW�B�{�I�ɂ���̂������̂œǂݎn�߂��B
���ɍ�i�̑����ɘR�ꂸ�A�ޔp�I�Ŏ��s�I�Ō����Č㖡���ǂ���i�����ł͂Ȃ��B
����ł��ǎ҂��������ޗ͂͗��ŁA���͂̏�肳�͓V�˓I�B�ȂɂȂ�̂��킩��B
�i2014�N12��4���Ǘ��j
-
�w�Ȃ�Ђ���d�폤�X�i�P���j�x�i���F�≪�q�T�G�j�m�C�u�j���OKC�n
�≪�q�T�G�̍�i�������B�ߖ����̉���������ɂȂ��Ă���n�[�g�E�H�[�~���O�ȍ�i�B
�����ɏo�Ă�������̏��q�吶����l���ŁA�������r�s�ɍs�����Ƃ��̏Ƃ��d�Ȃ�B
�o��l���̃L�����N�^�[�ɂ��ꂼ�����������̂ŁA����������Ȃ�W�J���y���݁B
�i2014�N12��1���Ǘ��j
-
�w�����������܂イ�̐X�i�P���`�S���j�x�i���F�≪�q�T�G�j�mNemuki+�R�~�b�N�X�n
�w�ǐH���{�b�g�x�Ɠ����≪�q�T�G�̍�i�ŁA���ɂ���s�v�c�ȐX�ł̕���B
��i�̐��E�ςɓǂݎn�߂ɂ͓���Ȃ��������A�����d�˂čs���Ύ��R�ɓǂ߂��i�B
�t�@���^�W�[���̂Ȃ̂łȂ��Ȃ��悪�ǂ߂Ȃ����A���Ȃ�W�J���y���݁B
�i2014�N11��28���Ǘ��j
-
�w���V��������ƁA���y�ɂ��Ęb������x�i���F���V�����A����t���j�m�V�����Ɂn
2010�N�`2011�N�ɁA����t�������V�����ɃC���^�r���[����`���ōs�����Βk�B
���y�ɑ����l�̃A�v���[�`������Ă��邱�Ƃ��A���̑Βk�̖ʔ����ł�����B
�}�[���[�̌����ǂ��������A�Z�~�i�[�̎�ނƑ吼���q�Ƃ̋����Ɏ���b�Ɋ��������B
�i2014�N10��29���Ǘ��j
-
�w���{��c�x�i���F�O�J�K��j�m���~�ɕ��Ɂn
2012�N�ɏo�ł��ꂽ�O�J�K��̏����ŁA2013�N�ɉf�扻�B�f��͂܂��ςĂ��Ȃ��B
�o��l�������X�Ƒ�����錻�݂̌���ŐS�̓�����葱���邾���Ȃ̂ɖʔ����B
�w�̂ڂ��̏�x�ɂ��o�ꂵ�����A�G�g�̃u���Ȃ��L�����͊ȑ��݊��ƍĔF���B
�i2014�N9��30���Ǘ��j
-
�w���m���[���˂��x�i���F���[���q�j�m���t���Ɂn
�w�ɂ�낶�[�x�ɑ薼�́u���m���[���˂��v�����^����Ă��āA�C�ɍs�����̂ōw���B
�S8�҂̒Z�ҏW�B�����̍��̋{���݂䂫�̃n�[�g�E�H�[�~���O�ȒZ�ҍ�i��f�i�Ƃ�����B
�u���v���܂ߎ��������̂̈Ӗ��������ɕ\���B���ɍŏI�b�́u�o���^���Ŋ��̓��v�͋������B
�i2014�N9��8���Ǘ��j
-
�w�̂ڂ��̏�i��E���j�x�i���F�a�c ���j�m���w�ٕ��Ɂn
2012�N�ɉf�扻���ꂽ����̗��j�����B���̖ʔ����A���؏܃m�~�l�[�g�A�{����ܑ�2�ʂ�������B
�E��̓���E���c�����]�Z��́u���e�v�i���̂ڂ��l�j�͎��݂̐l���ŁA�ƂĂ����j�[�N�Ȑl�B
����Ȃ��Ďd�����Ȃ��̂����ǁA�Ȃ����l�]���������[�_�[�Ƃ����̂́A��͂�ŋ����B
�i2014�N8��26���Ǘ��j
-
�w�ɂ�낶�[�x�i�ҁF�����Ďq�j�m�V�����Ɂn
�u�L�D���Ɉ����l�͂��Ȃ��I�L�G�b�Z�C�L�Z�Ҍ��얼��20�ҁv�̑тɒނ��čw���B
�Ėڟ��A�{���A���V��A����t���c�Ȃ��B�X�����Ƃ̔L���Ԃ肪�ʔ��������B
��͂薼���c����Ƃ͕��͂���肢�Ɗ�������A�ǂ�ł݂�����Ƃ̔��@���o�����B
�i2014�N7��24���Ǘ��j
-
�w�ǐH���{�b�g�i�P���j�x�i���F�≪�q�T�G�j�m�W�p�Ёn
�Ɛl�������Ă����̂���ēǂށB�uGirls Jump�v�Ɓu�W�����v���v��2012�N�`2013�N�Ɍf�ځB
�ݒ肪�ӕ\��˂��Ă��Ėʔ����B���悭�n�[�g�E�H�[�~���O�Ńz�����Ɨ���Ƃ��낪�S�n�悢�B
����������i�͂Ђ�����Ɣ���āA���������Ăق����B�钆�ɓǂ�ł���Ƃ������̂���_�B
�i2014�N6��27���Ǘ��j
-
�wSPEC�i�T�`�V�j�x�i�r�{�F�����|�G�@�m�x���C�Y�F�L�c�����j�m�p�앶�Ɂn
TBS�̘A���h���}�̃m�x���C�Y�B�ԑg��1,2���������Ƃ��Ȃ��̂ŁA�����Ƃ��ĕ��ʂɓǂ߂��B
�r�{���m�x���C�Y�����̂�����A���X�N�̑䎌���킩��Ȃ��Ȃ��Ă���ӏ�������̂������c�O�B
�X�g�[���[�͖ʔ����A���҂�����̂ł܂����Ԃ�u���ēǂ�ł݂悤�Ǝv���B
�i�T�F2014�N5��28���^�U�F6��3���^�V�F6��10���Ǘ��j
-
�w�L��x�i���F���c�܂ق���j�m�o�t���Ɂn
�R�̘b����C�̔L��ʂ��ēW�J����B�����Ă���́A��C�̔L�̈ꐶ�Ƃ��d�Ȃ��čs���B
�l�Ԃ̐����̒��ɂЂ�����ƁA��������������Ƒ��݂�����̂Ƃ��ĔL��`�����Ƃ���ɍD���B
���X�g�͓ǂݐi�ނ̂ɂ��h���`�ʂ������������A�Ō�͉������z�b�Ƃ��邱�Ƃ��o�����B
�i2014�N5��21���Ǘ��j
-
�w�u�X�̓��ɗ����Ă�x�i���F������ށj�m�}�K�W���n�E�X���Ɂn
������ݐX�O���̑哇���K�̕v������Ƃ̗�����ނ��Ȃ̂��Ƃ��������G���A�ڋL���̂܂Ƃ߁B
�낭�ł��Ȃ����e�ƌ����Ό����Ȃ����Ȃ����A���ăh���}�������ꂽ�Ƃ������ƂŁB
�ǂ�ł���Ƃ������A�ǂݏI����Ă��炭���Ă���A������ƐS�Ɏh�����i��������Ȃ��B
�i2014�N5��13���Ǘ��j
-
�w�[���̏œ_�x�i���F���{�����j�m�V�����Ɂn
�Ƃ̖{�I�Ō������̂Ń~�X�e���[�̌ÓT��ǂ�ł݂邱�ƂɁB���{������i�͏��ǂ݁B
���a���\���閼��Ƃ������Ƃ��������āA�l���ݒ�ƃX�g�[���[�W�J���ʔ����B
��b�̌��t�g����g����P��Ɏ���������邪�A�����ČÏL�������Ȃ��Ƃ����̂������B
�i2014�N5��2���Ǘ��j
-
�w�����X�^�[�x�i���F�S�c�����j�m���~�ɕ��Ɂn
�S�c��i�͏��߂ēǂB�X�g�[���[�Ƃ��ẮA�قڗ\�z�ʂ�̓W�J�ł͂������B
���͂̃X�s�[�h���ƕ`�ʂ̏�肳�́A������������q��Ƃ̗͂������C�������B
�Ȃ��Ȃ��G�O���V�[�������������A���e���`�ɑ���m���邱�Ƃ��o�����B
�i2014�N4��15���Ǘ��j
-
�w�r�u���A�Ï��X�̎����蒟�T�@�`�x�q����ƌq����̎��`�x�i���F�O�� ���j�m���f�B�A���[�N�X���Ɂn
�u�r�u���A�`�v�����ɂT���ځB����ɂ��Ă��N�I���e�B�̉�����Ȃ��V���[�Y���̂��B
�l�琢��ɂ͂��܂�Ȃ���ˎ����́w�u���b�N�E�W���b�N�x�Ɋւ���m��Ȃ���������ꂽ�B
�x�q����̕�e���\�ɏo�Ă��āA�X�g�[���[�S�̂��ǂ�ȕ����ɐi�ނ̂������ꂩ��̊y���݁B
�i2014�N4��3���Ǘ��j
-
�w�Y�ޗ́x�i���F�I �����j�m�W�p�АV���n
�w���Ǝ��Ɂ`�x���ʔ��������̂ŁA���������������҂�2008�N�Ƀq�b�g�����{���ǂ�ł݂��B
����������Ėڟ��ƃ}�b�N�X�E�E�F�[�o�[�̍l��������ɐi�߂�_���ʔ����B
�Y�ނ��Ƃ͈������Ƃł͂Ȃ��̂��B����������CM�́u�F�Y��ő傫���Ȃ����v���v���o���Ă��܂��B
�i2014�N3��24���Ǘ��j
-
�w���Ǝ��ɂ��Ă킽�����v�����Ɓx�i���F�I �����j�m�������Ɂn
�e���r�̉���Ȃǂł�����̛݂I�����́u�A�G���v�f�ڂ̃R�����i2007.12.17�`2012.11.26�j��蔲���B
�k�Ђ�����ł��邽�߁A���̑O�ƌ�ł͕����������Ԉ���Ă���悤�ɓǂ߂�B
�}�C�m���e�B�[�Ƃ��Ă̋ꂵ�݁A�S�̊�����������Ă��āA�Ȃ��Ȃ��ǂ݂��������������B
�i2014�N3��6���Ǘ��j
-
�w�R�����V�I�I�x�i���F�O�舟�L�j�m�p�앶�Ɂn
�w�ƂȂ蒬�푈�x�ȗ��A�v���Ԃ�ɓǂ��̒��҂̍�i�B�s�v�c�Ȑ��E�ς����ƂȂ����Ă����B
�ǂ����Ă��ˋ�̎Љ���������ɂ͓��荞�߂Ȃ��A�O���̓_�����������㔼��C�ɓǂݐi�߂��B
�w�����̂̂悤�ŁA�X�|���̂悤�ŁA�ߖ��������̂悤�ŁA���߂đ̌�����nj㊴�������C������B
�i2014�N2��4���Ǘ��j

2013�N
-
�w�}���A�r�[�g���x�i���F�ɍ�K���Y�j�m�p�앶�Ɂn
�ɍ��i�炵����z�V�O�ȃV�`���G�[�V�����Ȃ���A���ꂪ�l�ɓ���݂̂���Ƃ���Ŗʔ��������B
���Ȃ茌�Ȃ܂������Ĕ��G��̈����b�̒��ɁA�l�ԂƂ́H���H��₢������Ƃ�����ނ炵�����Z�B
���X�g�̃I�`�������ƖY��Ă��Ȃ��S�������A�l�C��Ƃł���R�����낤�B
�i2013�N12��5���Ǘ��j
-
�w�q�A�E�J���Y�E�U�E�T���x�i���F�L�� �_�j�m�V�����Ɂn
������҂̎��s�̂��炷�����琶�܂ꂽ�ʏ�̏����ƁA�㉉���ꂽ��������ɒ��z��
���M�����Ƃ����ꕗ�ς�����p���������[���h��W�J�B�ǂ���̘b���ǂ݂��������������B
��b�ڂ̌㔼�̓W�J�͋������B���̍�Ƃɂ͂������������B���������NJ������B
�i2013�N11��10���Ǘ��j
-
�w�I�[�I�t�@�[�U�[�x�i���F�ɍ�K���Y�j�m�V�����Ɂn
������܂����āA���ǏE��Ȃ���������������ƁA������ƕs���̎c���i�B
�b�̑傫�ȓW�J���㔼�Ɍł܂�߂��Ă��邽�߁A�O���͏����_���������������B�{�l�H���A
���̍�i�������̍Ō�̍�i�B�����̍ŏ�������w�S�[���f���X�����o�[�x�Ȃ̂ŋ����B
�i2013�N11��1���Ǘ��j
-
�w�L�P���x�i���F�L�� �_�j�m�V�����Ɂn
�u�L�P���v�Ƃ́u�@�B���䌤�����v�̈��̂ŁA��w�̈�T�[�N���̖��O�ł���B
���̍�i�ł����̒��҂̌����̏�肳�ɒE�X�B��ςƋq�ς̍��������▭�Ȃ̂��B
�����Ă����̂悤�ɁA�\�z�O�̃G���f�B���O�ɂ��ܑB���ɂ�ł��܂��̂ł������B
�i2013�N10��4���Ǘ��j
-
�w�[����}�i�S���`�U���j�x�i���F��؍k���Y�j�m�V�����Ɂn
�R���܂łŒ��f���ĂĂ����̂��S������ŏI���܂ł̂�т�ƂP�����������ēǂB
�{���̖ړI�ł���f���[�`�����h���̃o�X���s���S���܂ŗ��Ă���Ǝn�܂����B
���������͂����C���p�N�g�͂Ȃ����O���R���̕������������B�S�Ɏc�閼�삾�����B
�i2013�N9��17���Ǘ��j
-
�w�R���挕�i��E���j�x�i���F�i�n�ɑ��Y�j�m�V�����Ɂn
���ٗ��s�ɊԂɍ��킹�邱�Ƃ����ӂ��ǂݎn�߁A�Ǘ������قɌ�������s�@�̒��B�Z�[�t�B
�ܗŊs����2010�N�ɕ������ꂽ���ٕ�s������A�����̖\���V�y���ΎO�z����y����B
�O�N���N�O�ɓǂw���n���䂭�x�Ɠ������ɘA�ڂ��Ă����Ƃ����̂������B
�i2013�N8��2���Ǘ��j
-
�w�[����}�i�P���`�R���j�x�i���F��؍k���Y�j�m�V�����Ɂn
�����Ɠǂ݂����Ǝv���Ȃ���A�Ɛl�������݂ʼnƂ̖{�I�ɕ���ł����A���ɏd�������グ���B
�l����w���̍��ɏo�ł��ꂽ��i�̂͂������A�܂������Â��������������A�S��͂܂ꂽ�B
��͂薼��͐F�����Ȃ����̂Ȃ̂��B�킯�����ĂR���Œ��f�B�����͂܂�����ĊJ����\��B
�i2013�N7��8���Ǘ��j
-
�w�e���}�G�E���}�G�i�U���j�x�i���F���}�U�L�}���j�mBEAM COMIX�n
���N�̂P�O���ɂT����ǂ̂ŁA�Ȃ��肪�悭�킩��Ȃ��Ȃ������A����ɂĊ����B
��҂��i�Ō�́j���Ƃ����ɏ����Ă���悤�ɁA��i�̃q�b�g�ɂ�肱���܂ň�������ꂽ�����B
����ł������Ŏ�肠�����b���Y��ɏI���ɂ����̂́A�ǎ҂ւ̎ӈӂƎ�ꂽ�B
�i2013�N7��2���Ǘ��j
-
�w�C�܂�����l�x�i���F�O�J�K��j�m�p�앶�Ɂn
1997�N6���Ɋ��s���ꂽ�P�s�{�̕��ɉ��B���҂�35�̎��̑Βk�W�Ȃ̂Ő����Ǝ����������B
���؈���q�A�\��K��A���c�Ђ���A�c�A�Γc���q�ƌv13���̏����Ƃ̊Ԃ̋C�܂������͋C�̑Βk�B
�����Â��҂̐l���m�肪��������Ă����l���ʔ������`����Ă���B������Ƌ��������B
�i2013�N05��27���Ǘ��j
-
�w���������ĂȂ��ہx�i���F�L�� �_�j�m�p�앶�Ɂn
�f�扻�̃^�C�~���O�ɍ��킹�ĕ��ɉ����ꂽ�̂ŁA�����w���B���R�f��͌��Ȃ��B
�O���̃e���|�̗ǂ��W�J���S�n�悢�B�㔼���u�R���v�f�������Ȃ��Ă���̂́A���҂̓����B
�������ʊ��̑Βk���ʔ��������B�����A�ό��ɂ��Ă���Ȃɐ[���l�������Ƃ͂Ȃ������B
�i2013�N05��21���Ǘ��j
-
�w�o�C�o�C�A�u���b�N�o�[�h�x�i���F�ɍ�K���Y�j�m�o�t���Ɂn
�ςȓo��l�����o�ė��āA�ނ��Ⴍ����Ȃ��Ƃ�����Ă���悤�ł��āA���͈�Ԃ܂Ƃ���������B
�����̈ɍ��i�̃p�^�[���ł��邪�A��͂�悹���Ă��܂��̂��A���������ǖʔ����B
�W�J�̃��Y�����ǂ��A��͂�Ō�Ƀz�����Ƃ�����Ƃ��낪�A�e�N�j�V�������Ȃ��Ɗ��S����B
�i2013�N5��5���Ǘ��j
-
�w��̍��i�P���`�V���j�x�i���F�r�� �O�j�m���N�T���f�[�R�~�b�N�X�n
�l�C������Ɛl�������n�߂��̂ŁA�֏悵�Ĉ�C�ɓǂB�l�C���o�闝�R���킩�����B
����ƂȂ�G�]�m�[�ł̎�l���̊w�������́A���`���悤�ł��āA���͂����ł͂Ȃ��B
���߂�ꂽ���[���̏��i��ł���i�Ǝv���Ă���j�ǎ҂ɂ́A���\�h���I�ȃX�g�[���[�Ȃ̂��B
�i2013�N5��5���Ǘ��j
-
�w�r�u���A�Ï����̎����蒟�S�@�`�x�q����Ɠ�̊�`�x�i���F�O�� ���j�m���f�B�A���[�N�X���Ɂn
����Ĕ���āA���Ƀe���r�h���}�ɂ܂łȂ��Ă��܂������A�����Č��Ă��Ȃ��B
����͈����b�̒��҂ŁA�ǂ݂��������������B������͂������₱�����Ȃ����A�l�Ԗ͗l���ʔ����B
���Ԃ��҂̓��̒��ɂ���ł��낤����̓W�J���Ȃ��Ȃ��ŁA����������i�Ɏd�グ�Ăق����B
�i2013�N4��10���Ǘ��j
-
�wMIX�i�P���`�Q���j�x�i���F�������[�j�m�Q�b�T�������T���f�[�R�~�b�N�X�n
�^�b�`�̕���̖��w��������ƂȂ��Ă���싅����B�Q�b�T���ɘA�ڒ��B
�^�b�`�Ƃ̊֘A��������悤�łȂ��悤�ŁA���̂������炩�ɂȂ�̂��H
�l���ݒ肪�ʔ����A����̓W�J���y���݁B���ς�炸�����ʂ��t���Ȃ����B
�i2013�N3��28���Ǘ��j
-
�w�����ꏏ���@�����ƍ�Ƃ̂��̂����脟�x�i�ҁF�V�����ɕҏW���j�m�V�����Ɂn
��Ɓi���ɂ͖{�Ƃ���ƂłȂ��l���܂܂��j�������ƌ��Ƃ̊W���������G�b�Z�C�B
���D���Ƃ��ẮA�\���ɒނ��Ĕ������������邪�A�ǂ݉����������Ėʔ��������B
�Ƒ��̈���A�o��̕s�v�c�A�ʂ�̂Ƃ���3�e�[�}�ɕ��ށB���ɍŌ�̃e�[�}�́E�E�E�B
�i2013�N3��21���Ǘ��j
-
�w�ĖڗF�l���i�P���`�P�T���j�x�i���F�ΐ�䂫�j�m�ԂƂ��COMICS�n
�N�̏��߂ɂ��܂��܃A�j���������̂����������ɓǂݎn�߁A���NJ��o���͑S�ēǔj�B
���b�́u�I�_�l�v�A��l�b�́u���v�ȂǁA������i�ɂ͂Ȃ��Ȃ��̖��삪�����B
���ƌ����čŋ߂̍�i�������ăg�[���_�E�����Ă��Ȃ��̂ŁA���ꂩ����y���݁B
�i2013�N3��20���Ǘ��j
-
�w�A���}�Ӂx�i���F�L�� �_�j�m���~�ɕ��Ɂn
��҂̂��Ƃ����ɂ��ƁA���R���Z�v�g�̓��A�����������̎q�o�[�W�����Ƃ̂��ƁB
�A���ɏڂ����Ȃ��l�ɂ͓r�����ꂪ�P���ɂȂ��ė������A��͂藬�A�Ō�ɗ܂�U��ꂽ�B
�{�ҏI���̌�̃J�[�e���R�[����2�b���Ȃ��Ȃ��ǂ������B2�b�ڂł��܂��܂��E�E�E�B
�i2013�N3��5���Ǘ��j
-
�w�r�n�r�̉��x�i���F�ɍ�K���Y�j�m�������Ɂn
�w�ǔ��V���x�[����2008�N10��3���`2009�N7��18���܂ŘA�ڂ���Ă�����i�B
�\�����̖���wSARU�x�i���w�فA2010�N11���j�ƑɂȂ�B���ݖ��ǁB
�ˑR����o�ꂷ��ȂǓ˔�ȓW�J�ɂ��ւ�炸�A�X�g�[���[�Ƃ��Ē��낪�����̂��������B
�i2013�N1��26���Ǘ��j

2012�N
-
�w�V���̍K���_�x�i���F�g�{�����j�m�t�V���n
�w������̉̂̒��Ԃ̃u���O�Ō������ēǂ�ł݂��B���̔ނƊ����邱�Ƃ����Ă��Ėʔ�������
������������ōl����c�K�E�s�K�Ƃ����܂��傤���A����������ōl���Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃł��B
�ŏI�I�ɂ͐e�a�̘b�ɂȂ��Ă��܂������肪�A���҂炵���B�x����Ȃ���A�����������F�肵�܂��B
�i2012�N12��18���Ǘ��j
-
�w�x�i�K�N�j�i�P�V���C�P�W���j�x�i���F�Βː^��j�m�r�b�O�R�~�b�N�X�n
���ɂ��̍�i�������B�^�ۗ��_����Ǝv�����A�Ō�͂����Ɏ����Ă����ȊO�͂Ȃ����Ƃ��v�����B
���������R���D���ł��邾���̊x�̐������́A�\���̎R���Ƃ��ʂ���Ƃ��낪����C�����ǂ������B
�܂��R�ɓo�肽���Ǝv�킹�Ă�����i���������ʁA�~�̎R�����͈ꐶ�o��Ȃ��Ɖ��߂ĐS�ɐ������B
�i2012�N11��4���Ǘ��j
-
�w�\���@�P�Ɠo���ҁ@�R���j�x�i���F�ێR�����j�m���}�P�C���Ɂn
�\���i�P�Ɠo���j�ŗL���ȎR���j�ɂ��Ẵm���t�B�N�V������i�B
�Ǎ��̓o�R�Ƃ̔��������������L���������ł͂Ȃ��A�ނ̐������ւ̓��ۂ�ǎ҂ɋ���������B
�R�Ƃ����Ώۂɗ��܂炸�́A�{���ɍD���Ȃ��Ƃ𑱂��邱�Ƃ̑���ɋC�t�����Ă��ꂽ�B
�i2012�N11��1���Ǘ��j
-
�w�e���}�G�E���}�G�i�S���C�T���j�x�i���F���}�U�L�}���j�mBEAM COMIX�n
�킯�����ĂT������ǂݎn�߂Ă��܂������߁A���ǂ�����x�S������ǂ݂Ȃ������B
�X�ɂR����ǂ̂���P�N�O�Ȃ̂ŁA�Ȃ��Ȃ��q����Ȃ��������A���ς�炸�ʔ����B
����������u�X�g���[�ւ̓W�J�ɂȂ����A���ꂩ����y���݁B
�i2012�N10��28���Ǘ��j
-
�w����L���O�x�i���F�ɍ�K���Y�j�m���ԕ��Ɂn
���ԏ��X�̎G���́u�{�Ƃ��v��2008�N4���`2009�N3���܂ŘA�ڂ���Ă�����i�B
�u���Ƃ����v�ō�Ҏ������Ă���悤�ɁA�u�����̏����Ƃ����͋C�̈قȂ���́v�������B
�X�g�[���[�Ƃ��Ă͌����ł͂Ȃ��̂����A���G��ɍŌ�܂œ���߂Ȃ������̂��c�O�B
�i2012�N9��10���Ǘ��j
-
�w�t���[�^�[�A�Ƃ��B�x�i���F�L�� �_�j�m���~�ɕ��Ɂn
�h���}������Ăn�`���Ă����̂͒m���Ă��邪�A��x���ς����Ƃ��Ȃ������B
�z�����Ă����b�ƑS������āA���Ȃ�w�r�[�ȃe�[�}�Ɋ�Â�����i�ŋ������B
����ł��ŏI�I�ɂ͋~��������A�O�����Ő��Ȍ����Ɏ����Ă�����҂̎�r�Ɍh���B
�i2012�N8��31���Ǘ��j
-
�w�R���r�j�̔����Ă͂����Ȃ��H�i �����Ă������H�i�x�i���F�n�ӗY��j�m�����핶�Ɂn
�~���I���Z���[�ɂȂ����w�����Ă͂����Ȃ��x�i�����j�̒��҂ɂ��R���r�j�ł̓ǂݕ��B
���i�����o���Ĉ��ɂ��Č���Ă���̂ŁA�������璷�ł͂����������A���Ȃ̂Ŋy���߂��B
�����Ă������H�i�������Ă���̂��ǂ��B�Ō�̂܂Ƃߕ����͂��ꂩ��H�i��I�ԎQ�l�ɂȂ邩���B
�i2012�N8��10���Ǘ��j
-
�w�r�u���A�Ï����̎����蒟�R�@�`�x�q����Ə����Ȃ��J�`�x�i���F�O�� ���j�m���f�B�A���[�N�X���Ɂn
���̃V���[�Y���ǂ��y�[�X�łR���ڂ��o�ŁB�������̌Ö{�������ۂɑ��݂��邩�̂悤�ȍ��o�������Ă��܂��B
���҂̖{�ɑ���[�������a���������X�g�[���[�́A���z�������ʔ����B
�����Â𖾂��Ă䂭�x�q����������́A����ǂ̂悤�ɓW�J���Ă䂭���낤���B�����܂��y���݁B
�i2012�N7��25���Ǘ��j
-
�w���_���^�C���X�i��C���j�x�i���F�ɍ�K���Y�j�m�u�k�Е��Ɂn
����G���́u���[�j���O�v��2007�N4���`2008�N5���܂ŘA�ڂ���Ă�����i�B
�O���͈ɍ��i�̓����̃��Y������������ꂸ�A�������Ȃ������B
�㔼�͓Ɠ��̐��E�ς�����ė��āA���Y�����ǂ��Ȃ�A�Ō�͑������ߕ��B�ʔ��������B
�i2012�N7��16���Ǘ��j
-
�w�r�u���A�Ï����̎����蒟�Q�@�`�x�q����Ɠ�߂�����`�x�i���F�O�� ���j�m���f�B�A���[�N�X���Ɂn
�Q���ڂƂȂ�V���[�Y�B��i�̕��͋C�ɂ�����Ȃ�Ɠ����čs���āA�X�ɖ��������������B
���ς�炸�T�X�y���X�I�Ȍ����L�������͋N���Ȃ����A�t�ɐS���I�ɐ[�������������B
��l���ƓX��̞x�q����Ƃ̐S�̋������▭�ŁA�����W�J��z�����Ă��܂��B
�i2012�N6��13���Ǘ��j
-
�w���{�l�̒m��Ȃ����{��R�x�i���F�֑����C���q�j�m���f�B�A�t�@�N�g���[�n
�R���ڂƂ��Ȃ�ƁA�ǂ��Ӗ��ł͗��������ė��������ŁA�����Ӗ��Ń����l�������������B
����������Ă��A����͑��ƕ҂ň���B����͊C�O�҂Ƃ������ƂŁA�w�_�E���B���`�x�A�ڊJ�n�炵���B
����ł́A�e���ł̎w�ł̐��̐������Ɩ�����̓�i�����l�A���A���m����j�̗R�������ɂȂ����B
�i2012�N6��9���Ǘ��j
-
�w�������@�S���Ђ炭35�̃q���g�x�i���F���썲�a�q�j�m���t�V���n
�e���r�����đΒk�̃C���^�r�����[�ŗL���Ȉ��썲�a�q����̂�����Ƃ����m�E�n�E�{�B
��������肢�̂ŁA�V���Ȃ��烊�Y���ǂ���C�ɓǂނ��Ƃ��o����B�Βk�̃G�s�\�[�h���ʔ����B
�������ǂ��炩�ƌ����Ɓu�����n�v�̐l�ԂȂ̂ŁA�ƂĂ������[���ǂނ��Ƃ��o�����B
�i2012�N5��23���Ǘ��j
-
�w�r�u���A�Ï����̎����蒟�@�`�x�q����Ɗ�ȋq�l�����`�x�i���F�O�� ���j�m���f�B�A���[�N�X���Ɂn
�u�{�̎G�����I�� 2011�N�x���Ƀx�X�g�e�� ��P�ʁv�Ƃ������ƂŁA���N�b��ɂȂ�����i�B
�T�X�y���X�d���Ăɂ�������炸�A�������Ƃ����W�J�A�l�����肷��悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ��B
����܂Ŗ���������Ƃ̂Ȃ����͋C�̖ʔ�����i���Ǝv�����B�o��l�����L�������������Ȃ��B
�i2012�N5��11���Ǘ��j
-
�w�O�C�̂�������x�i���F�L�� �_�j�m���t���Ɂn
���̕ӂʼnƂɂ���L��{���s�����̂ŁA���炭�x�e�B�U�肩����ƈ�N���炢�ǂݑ����Ă���B
����ɂ��Ă����̍�Ƃ͖{���ɏ�肢�B���̏�肳���nj㊴�ōő���Ɋ�����B
��O�b�̌����̂Ƃ���ŃO�b�Ƃ��ݏグ����̂��������̂́A�S�����ʐ�����Ɠ����������B
�i2012�N4��20���Ǘ��j
-
�w�V�A�^�[�I�Q�x�i���F�L�� �_�j�m���f�B�A���[�N�X���Ɂn
�w�V�A�^�[�I�x�̑��҂ł���A�O�N�Ԃ������Ă̎؋��ԍςɌ����Ĉ�ۂƂȂ錀�c�̕���B
�O��ɔ�ׂĂ��l�̐S��̕`�ʂ������Ȃ�A�����ɂ͓��R�F���̊��������Ă���B
�l���W�܂�Ή���������͋N���邯�ǁA��������Ƃ����ĉ������邱�Ƃ��܂��y�����̂��B
�i2012�N4��6���Ǘ��j
-
�w�x�i�K�N�j�i�P�U���j�x�i���F�Βː^��j�m�r�b�O�R�~�b�N�X�n
�V�����W�J�łǂ��Ȃ邱�Ƃ��Ǝv�������A���̕ύX������t�����悤�Ŗʔ��������B
����������ł̌��݂̏����݂A�X�g�[���[�̐i�ߕ�����肢�Ǝv�����B
�V�F���p���t���悤�ȎR�ɂ͈ꐶ�o��Ȃ��Ǝv�����A�R��������҂Ƃ��Ă͂킭�킭����B
�i2012�N3��16���Ǘ��j
-
�w�V�A�^�[�I�x�i���F�L�� �_�j�m���f�B�A���[�N�X���Ɂn
����Ȃ����c�u�V�A�^�[�E�t���b�O�v�̗��Ē����ɖz�����錀�c��ɂ̌Z�̕����L�B
�˔\������̌��c��ɂ̒�ɔ���Ȃ������猀�c��ׂ��ƌ��������ɌZ�̒�ɑ���[�������������B
���c�Ȃ荇���c�Ȃ�Ƃɂ����l�O�ʼn����邱�Ƃ��o�������l�ɂ͂ƂĂ������o�����i�B
�i2012�N3��16���Ǘ��j
-
�w34���E����x�i���F�������������j�m���f�B�A�t�@�N�g���[�n
�R�~�b�N�t���b�p�[�ɘA�ڂ��ꂢ���Ƃ̂��ƁB�����������ɒu�������Ă��܂���i�ł���B
���ł��������^�ʖڂɐE��ɒʂ��Ă��邪�A��Ђɍs�������Ȃ��Ȃ��������Ɋ������C�������S��B
�u��N�ԉ��������ɂ��悤�ƌ��߂��v�Ƃ����`���̕��͂����G�ɋ��ɓ˂��h����B
�i2012�N2��28���Ǘ��j
-
�w�N�W���̔ށx�i���F�L�� �_�j�m�p�앶�Ɂn
�w�C�̒�x�A�w��̒��x�̔ԊO�҂��R�ғ����Ă��āA����ȊO�����q�����W���郉�u�R���B
���Ƃ����Œ��Җ{�l���u���q�����u�R���V���[�Y�v�Ƃ������s�I�i�H�j�Ȍď̐錾�����Ă���B
��q����i��ǂ�ł��班�����Ԃ��o���Ă���̂ŁA�������ĐV�N�Ŗʔ��������B
�i2012�N2��26���Ǘ��j
-
�w���C���c���[�̍��x�i���F�L�� �_�j�m�V�����Ɂn
�w�}���ٓ����x�̕���̒��ɏo�ė����{�ŁA���o��Q���������Ƃ��̏����Ɏ䂩���j���̘b�B
�������̂悤�Ȏ���c�����A���e�����Ƃ��Ă̌��t�������Ƃ��Ă̌��t�̊Ԃɗh�ꓮ�����������B
�����҂Ƃ������t�ȂǁA����܂Œm��Ȃ��������o��Q�ɂ܂��l�X�Ȏ��ۂ�m�邱�Ƃ��o�����B
�i2012�N2��17���Ǘ��j
-
�w��������{��x�i���F���R�O���j�m���~�ɕ��Ɂn
���܂��ܖ钆��NHK�����Ă�����A���̌�������ɂ����h���}����f���Ă����̂��ʔ��������B
�����ǂ�ł݂����Ȃ�A���̓��̂����Ƀl�b�g�Ń|�`���ƁB�����Ƃ����ԂɓǂݏI����Ă��܂��B
���҂͉f��w������тƁx�̋r�{�Ƃ������ŁA����_���ƂĂ����j�[�N�ň������܂ꂽ�B
�i2012�N2��6���Ǘ��j
-
�w�ʍ��@�}���ِ푈�U�x�i���F�L�� �_�j�m�p�앶�Ɂn
�ԊO�҂Q���ڂŁA�����S�����ɓn���ēǂݑ������w�}���كV���[�Y�x������ɂđS�ďI���B
�w�`�T�x�Ɠ������u�R���H���ł͂�����̂́A�e�[�}�ƃX�g�[���[�W�J�̖����ʔ��������B
�u�������^�C���}�V������������v�̏��`�������̘b���������B�Ō����߂�����ɒl�������B
�i2012�N2��1���Ǘ��j
-
�w�ʍ��@�}���ِ푈�T�x�i���F�L�� �_�j�m�p�앶�Ɂn
�w�}���كV���[�Y�x�̖{�҂͂S���Ŋ������Ă��邪�A��l�̎���i��Ғk�j�ŏo�����X�s���A�E�g���́B
��҂͂��Ƃ����Łu�x�^�Áv�A�u�ǂ܂Ȃ��Ă��x��Ȃ��v�ƌx�����Ă��邪�A���Ƃ����Ō����Ă��B
�Ƃ͂����A����܂œo��l���̃L�����N�^�[�Ɋ���e���l�ɂƂ��Ă͖ʔ���������Ǝv���B
�i2012�N1��21���Ǘ��j

2011�N
-
�w�}���يv���x�i���F�L�� �_�j�m�p�앶�Ɂn
�w�}���كV���[�Y�x�Ƃ��Ă͑�S���ځi�ŏI���j�ɂ������i�B���ߕ��A�`���̌��������ɔ������Ă��܂��B
��͂肱�̃V���[�Y�̌����������Ƃ͂����ɂ������̂��Ɣ[��������ŏI���B
�e���̍Ō�ɏ�����Ă����҂Ǝ��ʐ�����Ƃ̑Βk�����ɖʔ��������B
�i2011�N12��29���Ǘ��j
-
�w�Ƃ�ς�i�Q���j�x�i���F�Ƃ�̂Ȃ�q�j�m�u�k�Ёn
�肽���Ԃɂ��A�P�C�R�̎��ɂ��̂Q���B�~�̊��̗l�q���`����Ă��Ėʔ����B
���܂���̂��܂���Ƃ̓���A�����Ă��܂���Ƃ̕ʂ�A�����Ȗ��ɂ����������������B
�߂��ė����c�O�~�̂��݂�A���u���[�ȃG�i�K�A���o��A�J�Q���̃y�������ȂǃL�������o�B
�i2011�N12��15���Ǘ��j
-
�w�}���ي�@�x�i���F�L�� �_�j�m�p�앶�Ɂn
�w�}���كV���[�Y�x�Ƃ��Ă͑�R���ڂɂ������i�B�o��l���̃L�����N�^�[����܂��ė����B
�O�̂Q���Ɣ�ׂ�ƁA�傫�ȕω�������A���[�������܂œ��荞��ł��銴���B
���t���̌����A���ۂ̐퓬�V�[���ȂǁA��҂��{�ɑ��鈤����\�̒��ɕ`����Ă���B
�i2011�N12��1���Ǘ��j
-
�w�}���ٓ����x�i���F�L�� �_�j�m�p�앶�Ɂn
�w�}���كV���[�Y�x�Ƃ��Ă͑�Q���ڂɂ������i�B�o��l���́w�`�푈�x�Ɗ�{�I�ɂ͓����B
�V�����o��l���́A�܂����ꂼ��ɓƓ��̃L�����N�^�[�ŁA�b�̍L���肪�S�n�悢�B
���\�̐��E�Ƃ͂����A�F�X�ƍl������������e�ŁA�{�Ƃ͉����H�����Ă���C������B
�i2011�N11��15���Ǘ��j
-
�w�e���}�G�E���}�G�i�Q���C�R���j�x�i���F���}�U�L�}���j�mBEAM COMIX�n
�Q���͂����Ȃ胍�[�}����ɂ�����A���{�Ō����Ƃ���̋����M����n�܂�B
��b�����̃p�^�[������A���b�ɓn���i���o�ė��āA���C���̂��̂Ƃ��������A
���C�̎��ӂ̕����ɂ��Č����B�y���݂Ȃ��炻�̎���̕������w�ׂĖʔ����B
�i2011�N11��14���Ǘ��j
-
�w�e���}�G�E���}�G�i�P���j�x�i���F���}�U�L�}���j�mBEAM COMIX�n
���̑O�m�����Ȃ��܂܁A�肽�{��ǂݎn�߂��B���̍�i�Ƀn�}��̂͂ƂĂ��킩��B
�Ȃ��Ȃ炱��܂łɂȂ��W�J�̖��悾���炾�B�Ñネ�[�}������]�~���[�܂�̂��������B
���҂ɂ��u���[�}�����C�A�킪���v�Ƃ����G�b�Z�C���ʔ����B
�i2011�N11��4���Ǘ��j
-
�w�}���ِ푈�x�i���F�L�� �_�j�m�p�앶�Ɂn
��҂̏o����Ƃ�������w�}���كV���[�Y�x�̑�P���ڂ̍�i�B���R���ւƓǂݐi�ޗ\��B
�͂���߂���Ȑݒ�ł͂��邪�A�ŋ߂̐��̒��̓���������ƊG�Ƃ͎v���Ȃ��B
�o��l���̃L�����N�^�[�Ɋ���Ă��܂��A����Ȃ�Ɠǂݐi�߂ĂƂĂ��ʔ����B
�i2011�N10��31���Ǘ��j
-
�w�Ƃ�ς�i�P���C�R���j�x�i���F�Ƃ�̂Ȃ�q�j�m�u�k�Ёn
���߂͉��ƂȂ������ǂ���̂Ȃ��̂Ȃ���i���Ǝv���Ă������A���̊Ԃɂ��y�[�X�Ƀn�}��B
���҂������Ă���悤�ɁA�m���ɖ쒹��`��������͂���܂Ō������Ƃ��Ȃ������B
��b�i��H�j���Ƃ̎��I�ȍŏI�y�[�W���A�����܂ł̂�����炯�ƈ�����悵�Ă��Ď������B
�i2011�N10��30���Ǘ��j
-
�w�x�i�K�N�j�i�P�T���j�x�i���F�Βː^��j�m�r�b�O�R�~�b�N�X�n
�f�扻���ꂽ�肷��ƃe���V�����������Ă��܂��̂����̏�ł��邪�A���̍�i�͈Ⴄ�悤���B
�����}���l�������Ă������߁A��b�ǂݐ�Ƃ��������A���������߂̃X�g�[���[�ɕύX�B
�V�����W�J�ɔ������ꂩ��̊x�̍s������ڂ������Ȃ��Ȃ����B��������ނ���ς������B
�i2011�N10��15���Ǘ��j
-
�w���̊X�x�i���F�L�� �_�j�m�p�앶�Ɂn
�w�C�̒�x�A�w��̒��x�Ɏ����ŁA�u���q���O����v�̈��ڂŃf�r���[��́w���̊X�x�B
��i�Ƃ��Ă̊����x�͊��S�łȂ��Ă��A���Ƃ����ō�҂������Ă���悤�ɁA
�u���������悤�ɏ������v�Ƃ����_�ɍD�������Ă�B�Ⴓ�̟̂Ӑg�̍�i�ƌ����邾�낤�B
�i2011�N9��30���Ǘ��j
-
�w�G�ߕ��@�H�x�i���F�d�� ���j�m���t���Ɂn
�����҂Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A�Ō�ɕ��ɉ����ꂽ�w�H�x�B����Ŏl�G����������ƂɂȂ�B
�W�b�ڂ́u�E�C�j���O�{�[���v����ԗܑB�ɗ����B���̎�̐ݒ�͒�Ԃ����ǁA��͂�ア�B
�d�����[���h�͂܂����炭������ꂻ���ɂȂ��������̍��Ȃ̂ł������B
�i2011�N9��12���Ǘ��j
-
�w�G�ߕ��@�āx�i���F�d�� ���j�m���t���Ɂn
���ɉ����ꂽ�̂ŁA�w�~�x�A�w�t�x�ɑ����ēǂ�ł݂��B���~�̍��ɂ͓ǂݏI�����������̂ŊԂɍ������B
��҂����Ƃ����ŏ����Ă���悤�ɁA�P�Q�҂̒Z�҂̓��e�����Ɋ֘A�������̂����������B
�Q�b�ڂ́u���������A�h��āv�ɂ͂Ȃ������ꂽ�B�c�{�Ȃ̂�������Ȃ��B
�i2011�N8��16���Ǘ��j
-
�w�G�[�X���˂炦�I�i�P���`�P�S���j�x�i���F�R�{������j�m�������ɃR�~�b�N�Łn
���݂̉̂̒��Ԃ��b��ɂ����Ƃ��A�u���\�X�|�����m�D���Ȃv�̈ꌾ�ő݂��Ă��ꂽ�B
�O���ɔ�ׂČ㔼�����ʔ��݂ɂ�������̂́A�����ł�߂��͈̂̂��Ǝv���B
�l�̒��ł͍ŏI�I�ɁA����͉��Ђ�݂ł͂Ȃ��A����퍁�i�����v�l�j�ɂȂ��Ă��܂����B
�i2011�N08��05���Ǘ��j
-
�w��̒��x�i���F�L�� �_�j�m�p�앶�Ɂn
�ȒP�Ɍ����ƁA�w�C�̒�x�͊C�㎩�q��������ŁA�w��̒��x�q�q��������ł���B
�w�C�`�x������ɏ����ꂽ��i�̂悤�����A�c�{��������Ɖ������Ă��閼�삾�Ǝv���B
���X�g�V�[����ǂ͉̂�ЋA��̓d�Ԃ̒��������̂����A�܂�}����̂ɋ�J�����B
�i2011�N08��04���Ǘ��j
-
�w��}�d�ԁx�i���F�L�� �_�j�m���~�ɕ��Ɂn
�L���i�������Ă��邪�A����͂��܂��܁B�̂̒��ԂɐS���܂�ʔ�����i�ƑE�߂��Ď肽�B
���N�̃R���N�[���ōs�����_���ł͂܂��ɍ�}�d�Ԃɏ�����̂ŁA�z���o�[���H���ł�����B
���g�����������A�X�g�[���[�̍�������肢�Ȃ��ȂǂƁA�e�N�j�b�N�I�Ȃ��̂ɂ������o�����i�������B
�i2011�N05��16���Ǘ��j
-
�w�x�i�K�N�j�i�P�R���`�P�S���j�x�i���F�Βː^��j�m�r�b�O�R�~�b�N�X�n
�f�扻�ł������胁�W���[�ɂȂ��Ă��܂��A�V�̎S�Ƃ��Ă͂�����Ǝc�O�B�f��͌��Ȃ����B
���ς�炸���O���̂��̃L�����N�^�[�̗ǂ��Ɗ���ɂق��Ƃ�������B
�P�S���̑�O���u�R�̗D�������v�͔�������Ȃ��Ǝv���Ȃ�����A�����b�𖡂킦���B
�i2011�N05��15���Ǘ��j
-
�w�C�̒�x�i���F�L�� �_�j�m�p�앶�Ɂn
�g���b�L���O�̒��Ԃ���E�߂��Ď�ēǂ{�B�P�Ȃ���b�f��̂悤���������ł͂Ȃ��B
�����͂̒��ŌJ��L������l�Ԗ͗l�A���n�ŌJ��L������|�����A�X�������O�Ŋ�������B
����X���A����ƂȂ����{��̒n��W�]�䂩�璭�߂��̂������āA�ƂĂ����A���Ŋy���߂��B
�i2011�N05��05���Ǘ��j
-
�w�R�o��͂��߂܂����Q�x�i���F��Ƃ����j�m���f�B�A�t�@�N�g���[�n
�R���q�u�[���̉Εt����I�ȃR�~�b�N��Q�e�B����̐l�����l���n�}���Ă���B
����́A���Ô����R�A��O�x�A�����x�E�V��x�A���v���E�{�V�Y�x�A�����x�B
���v���ɂ������x�ɂ��s���Ă݂����Ȃ����B��͂�C���R�ɖ��͂�������B
�i2011�N04��27���Ǘ��j
-
�w�F�ʂ̑��q�x�i���F�R�c�r���j�m�V�����Ɂn
�Ō�̉���̌��t�����ƁA���i�A�����A�،h�A�M��A�����A�����A�Ƃ��߂��E�E�E
����Ȋ���F�ƂƂ��ɒԂ�ꂽ�ِF�̒Z�ҏW�B�{���ɐF�̒������y�[�W���ʔ����B
�N�ł����Ȃ��炸�����Ă���S�̉A�̕��������A���ɕ`����Ă��ăh�L���Ƃ���B
�i2011�N4��10���Ǘ��j
-
�w����悤�ȂȂ��悤�ȁx�i���F���O���j�m�������Ɂn
���҂��w�ւށx�ŊH��܂���������̊e���Ɍf�ڂ��ꂽ�G�b�Z�C�W�B
���͂��������Ƃɑ��ăK�c�K�c���Ă��Ȃ������ɂƂĂ��D��ۂ��������B
���̒����ÂɌ��Ă���悤�ȁA�ӂ�ӂ핂�V���Ă���悤�ȕs�v�c�ȍ�i�Q���B
�i2011�N3��17���Ǘ��j
-
�w�v�`�˂��i�S���j�x�i���F�k�����K�j�m�A�t�^�k�[��KC �u�k�Ёn
�L�Ƃ����������͂ǂ����Ă��̂悤�ɂ��Ȃ₩�ŊԔ����ŏ���̂��낤���B
�����Ă���Ƃ��������A���������ɓ�����O�̂悤�ɂ���Ƃ����X�^���X�������B
�L�̕\������܂Ŏ��R�ȔL������Ȃ��Ȃ��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ɗ��S����B
�i2011�N3��13���Ǘ��j
-
�w�G�ߕ��@�t�x�i���F�d�� ���j�m���t���Ɂn
�w�G�ߕ��@�~�x�ɑ����ēǂ�ł݂��B������Ƒ����������A�G�ߓI�ɂ������Ȃ��B
�w�`�~�x�����S�ɃO�b�Ƃ���b�����������悤�Ɋ�����B���Ă��ꂽ�B
�u�����m�v�A�u�ڂɂ͐t�v�A�u�c�o���L�O���v�̂R�̘b�����ɗǂ������B
�i2011�N3��4���Ǘ��j
-
�w�G�ߕ��@�~�x�i���F�d�� ���j�m���t���Ɂn
�O����C�ɂȂ��Ă�����ƂŁA�Ƃ肠�����Z�҂���ǂ�ł݂邱�Ƃɂ����B
�Z���`�����^���ƃm�X�^���W�[�������ۂ��Ȃ��O�̐▭�ȍ������ŕ\�����Ă����ہB
���҂Ɩl�̔N��߂��̂��A��i�ɓ��荞�߂�v���ɂȂ��Ă���B���炭�n�}�肻���B
�i2011�N2��24���Ǘ��j
-
�w�S�[���f���X�����o�[�x�i���F�ɍ�K���Y�j�m�V�����Ɂn
�f��ɂ��Ȃ��Ęb��ɂȂ������ґ��B�G���^�[�e�C�������g���w�Ƃ��đf���炵����i�B
�X�s�[�h���A��z�V�O�ȓW�J�A���̒��ɎU��߂�ꂽ�����A�����Ĉɍ��i�Ɠ��̋��D�B
���Z�Ȃ͂��Ȃ̂ɁA��i�̑n����d�˂�ɂ�āA�܂��܂��������������Ă���̂������B
�i2011�N1��18���Ǘ��j

2010�N
-
�w�����Ă͂����Ȃ��I�x�i���F���q�q���j�m�u�k�Ёn
���͂ƂĂ������ɂ������A�W���b�N�E���b�Z���E�e���A�������Ă��钘�҂̃G�b�Z�C�B
�ʐ^�������Ȃ���A���ǂ͂��̌���A�����Ĉ����̗ǂ��Ƃ�����Љ�Ă䂭�{�B��e�o�J�B
���D���ɂ͂��܂�Ȃ����e�ł���Ɠ����ɁA�����������Ƃ̑�ς����ĔF���ł���B
�i2010�N12��29���Ǘ��j
-
�w�܂ڂ낵�n���C�x�i���F�悵���ƂȂȁj�m���~�ɕ��Ɂn
�O�҂̕ʂ̕��ꂪ����ɋl�܂��Ă���{�B���̍���ɂ́A�S���ʂ����D�荞�܂�Ă���B
�n���C�Ƃ����ꏊ�͂������ʂ����琶�܂�鈣���݂�S�Ď���Ă����B
���҂��ܔN�����ď�������i���������āA���t���̐S�ւ̐Z���͂ɋ������ꂽ�B
�i2010�N12��1���Ǘ��j
-
�w�����x�i���F��؍k���Y�j�m���~�ɕ��Ɂn
���q�͂ǂ̂悤�ɕ���������̂��H�i�т��j�E�E�E���̌��t�ɋÏk���ꂽ���e�B
�}�炸���w�����^���[�x�ŕ�̎���ǂ�ɁA���̎��ɂ��ēǂނ��ƂɁB
�������앗�͑ΏƓI�ŁA������͒��ғƓ��̒W�X�Ƃ��������̂̈��������`����Ă���G��B
�i2010�N11��2���Ǘ��j
-
�w�����^���[�@�|�I�J���ƃ{�N�ƁA���X�A�I�g���|�@�x�i���F�����[�E�t�����L�[�j�m�V�����Ɂn
�\�z�ʂ�A�Ō�̕��ł͉��x���܂����B���̎�̓��e�ƓW�J�̓Y�����Ǝv���A
���b�ł��邾���ɁA���҂ɂƂ��Ă������Ċy�ɒ������킯�ł͂Ȃ����낤�B
�����đ����ɘR�ꂸ�A�������A���C�Ȃ����ɐe�F�s���Ă����Ȃ��Ắc�Ǝv�����B
�i2010�N9��21���Ǘ��j
-
�w���y�̒������@�����^�Ǝ����錾�t�x�i���F���c�Ő��j�m�����V���n
�����̂悤�ɂ���Ȃ�Ƃ͓ǂ߂Ȃ����A�Ȃ�ق��Ƃ����邠���Ƃ����������Ȃ���e�B
�ʔ��������L�[���[�h�́A�u���Ȃ�}���فv�A�u�킴����v�ȂǑ����B
�Ȃ�Ȃ�ɂ��A�u�ӏܓ��L�v�ʼn��y��������肵�Ă���̂ŁA�ƂĂ��Q�l�ɂȂ����B
�i2010�N8��31���Ǘ��j
-
�w���p��b�x�i���F���V�����~�k���剀�j�m�ʐ}�Ёn
���Ɛ���������ǂ��̂��A�Ƃɂ�������{�B�тƕ\���ɏ����Ă�ᕶ�����̂܂����Ă������B
�u�ǂ��Ŏg���A����ȉp��!? �Q�l����p��b�{�ɍڂ��Ă���"���肦�Ȃ�"���Ηᕶ140�A��!�v�B
�u�T�C�����͉e�������v "Simon's presence is not felt strongly."�E�E�E�C���X�g���܂������I
�i2010�N7��31���Ǘ��j
-
�w��u�̉āi��E���j�x�i���F��؍k���Y�j�m�V�����Ɂn
�O����ǂ����Ǝv���Ă������A��؍�i��ǂ̂͏��߂āB�������t�@���������̂��킩��B
�J�V�A�X�����c�����ȃ{�N�V���O�t�@���̋L���̒��ɂ������Ȃ��{�N�T�[�̖��O�B
���������炩�ɂ���u�ԁA���E�Ƃ������̂��ڑO�ɂ������{�N�T�[�������̂��A�����ƁB
�i2010�N7��29���Ǘ��j
-
�w�b�q���̋�ɏ��I�x�i���F�쌴 ��j�m����Е��Ɂn
�w���C�v����L�x�ŃX�C�b�`�������Ă��܂��A��������P�O�N�ȏ�Ԃ�ɍāX�ǁB
�w�b�q���̋�ɏ��I�x�A�w�Q�[�g�{�[���E�l�����x�A�w��̃��}���e�B�b�N�c��͂́x�̂R�b���^�B
�Ō�́w��́`�x�̃|�`�̑�Z�ɑS�Ă������čs���ꂽ�����B�쌴��i�̃S�[���͂�͂��Ί��B
�i2010�N7��27���Ǘ��j
-
�w���C�v����L�i�P���`�Q���j�x�i���F�쌴 ��j�m����Е��Ɂn
�P�O�N�ȏ�Ԃ�ɍāX�ǁB�w�b�q���̋�ɏ��I�x�̑��҂����A�ʌɓǂ�ł��ʔ����B
���̐l�̊G�́A�l���̔��̖т̕`�������D���B�����ƂĂ��������B
����̏I�������A�唚�̊쌀�̌�̂ӂ��Ƃ����₵�����܂�ł��ċ�����B
�i2010�N7��19���Ǘ��j
-
�w�x�i�K�N�j�i�P�Q���j�x�i���F�Βː^��j�m�r�b�O�R�~�b�N�X�n
�ŏ��̊��̍��Ƃ͂����ԕς���Ă��Ă��邪�A����͂���Ŗ��킢������B
��P���u�T�C�����g�E�i�C�g�v�łق��B��R���u�R�����v�����ꐫ�������ėǂ������B
�~�R�ɂ͌����ēo��Ȃ��ƌ��߂Ă���̂ŁA�{�̒������Ŋy�������B
�i2010�N7��9���Ǘ��j
-
�w�b�i�P���`�P�O���j�x�i���F�▾ �ρj�m�A�t�^�k�[���j�b�n
�ߋ��ɂ��̊G�̃G�O���œr�����܂�����i�B�Ƃ��炵����Ȃ��Ȃ����̂œǂ߂��̂����B
1990�N�㒆���ɂ��������e�[�}�ŏ����Ă������ƂɁA���҂̗ނ܂�ȍ˔\������B
�s��Ȑ킢���犴���I�ȃ��X�g�V�[���Ɍ���������B����ƌ����闝�R���킩��B
�i2010�N7��2���Ǘ��j
-
�w�̂��߃J���^�[�r���i�P���`�Q�R���A�Q�S���j�x�i���F��m�{�m�q�j�m�u�k�Ёn
�O���͂Q�O�O�S�N�ɔ����Ă���悤�Ȃ̂ŁA��u���C�N����O�������͂����B
����܂łɗ��w�������̘b�܂ł͓ǂ�ł������A���̌�ڍ����Ă��B�V�̎S�Ȃ̂ŁB
��͂藯�w����O�̘b�̕����ʔ��������B�ł��ŏI�b�i�Q�R���j�̏I�����͗ǂ������B
�i2010�N6��6���Ǘ��j
-
�w�_�l�̃{�[�g�x�i���F�]�����D�j�m�V�����Ɂn
���z�Ƃ̕�̌��ň�����A�����ƂƂ��Ɍ����I�ɂȂ��Ă䂭�B���ȃ��A���e�B��������B
�Q�l�̏����̐S�̓������A���݂Ɍ����W�J���ǂ������b�I�ł���Ȃ���A���̓I�B
����Ƃ̍�i��ǂ̂͊m���Q���ځB�G�N�j�E���[���h�Ƀn�}��l�̋C�������킩��B
�i2010�N5��27���Ǘ��j
-
�w���q�̂���X�i�P���`�S���j�x�i���F�▾ �ρj�m�u�k�Ж��敶�Ɂn
�P�O�N�ȏ�O�ɔ����ė����{�̓ǂ݂Ȃ����B�A�ڂ��ꂽ�Ƃ�������y���݂ɂ��Ă�����i�B
���C�ňÂ�������l���̕��q���A�l�Ƃ̂ӂꂠ����ʂ��ĕς���Ă����p��������Ɗ����I�B
���������������Ƃ������Ԃ̗���̍�i�����̍��̃��[�j���O�ɂ͑�R�ڂ��Ă����B
�i2010�N5��8���Ǘ��j
-
�w�v�`�˂��i�P���`�R���j�x�i���F�k�����K�j�m�A�t�^�k�[��KC �u�k�Ёn
�L���̖̂���͐��������邪�A�L�̃��A���ȕ`�ʂ����o�B���킶��Ə������ݏグ��B
�����l���Ă��Ȃ��̂�������Ȃ��̂ɁA�����l���Ă���Ɗ���������L���L�̍s�����ʔ����B
�R���ڂɌ����Ăǂ�ǂ�p���[�A�b�v���Ă��銴���B�R�����o�ĊۂQ�N�B���������Ă݂����B
�i2010�N5��1���Ǘ��j
-
�w�����x�i���F�����a���j�m�͏o���Ɂn
�Ǔ���Q�e�B�o����ł����邵�A�f�扻����Ęb��ɂȂ����̂��o���Ă���B
����͒��҂Ɩl�̋��ʂ̌̋��ŁA�`����Ă��鎞���ɖl���g�����̓y�n�Ő������Ă����B
�����Ė��邢��i�ł͂Ȃ����A�w�����x�Ɠ����悤�Ȏ�҂̊����������ɕ`����Ă���B
�����́u���҃m�[�g�@�����̕��i�v���A�ނ���{�҂����S�ɋ������B
�i2010�N4��22���Ǘ��j
-
�w�ڂ��͕����ł��Ȃ��x�i���F�R�c�r���j�m�V�����Ɂn
���Ƃ����Œ��҂��ȉ��̂悤�ɏ����Ă���Ӗ����A�ǂݏI���Ă݂�Ƃ悭�킩��B
�u��l���̎��c�G���͍��Z�������A���́A�ނ���A���̖{���l�̕��ɓǂ�ł������������Ǝv���B�v
���̖{�́A�����ĖY��Ă͂����Ȃ��{���ɑ�Ȃ��̂��v���o�����Ă����{�Ȃ̂��B
�i2010�N3��22���Ǘ��j
-
�w�x�i�K�N�j�i�P�P���j�x�i���F�Βː^��j�m�r�b�O�R�~�b�N�X�n
��b��b�̕���Ƃ��Ă̊����x�������d�˂邲�Ƃɍ����Ȃ��Ă���C�����邪�A
�ǂ�ł��邾���Ŋ������R�̓��������炬�A���ʂ̃n�[�g�E�H�[�~���O�n�ɂȂ��Ă��邩�H
��R���u�t���C�h�`�L��������B�v�ł͕s�o�ɂ��܂��Ă��܂����B
�i2010�N3��18���Ǘ��j
-
�w�M����x�i���F���O���j�m���t���Ɂn
�{�I�ɕ���ł����̂�ǂݎn�߂�B����i�͉����ڂɂȂ邩�B���ς�炸�s�v�c�Ȑ��E�B
�ޔp�I�ƈꌾ�ōς܂��Ă��܂����Ƃ��o���邪�A�Ȃ������ɖ��邢�B
���܂育�Ƃł�����߂̐��̒��ɔ�ꂽ��A����������i�ɐG���̂��ǂ������B
�i2010�N3��14���Ǘ��j
-
�w�����x�i���F�����a���j�m�W�p�Е��Ɂn
�挎�ɂ��܂�}�����������a�������1982�N�̍�i�B�V���b�N�������B
�w�юɂ��������y�ւ̒Ǔ��̈Ӗ������߂āA�{�I�ɕ���ł����̂�ǂݎn�߂�B
�Ⴓ�䂦�̏������A���d���A�L����`���A����Ӗ����낵�������ցB
�i2010�N3��5���Ǘ��j
-
�w�H�������ނ�x�i���F���쎅�j�m�|�v�����Ɂn
���ŋ߉f�扻���ꂽ�q�b�g��B�f��̕��͖l�ɂ͊W�Ȃ����B
�H�ׂ邱���̏d�v���ƁA�H�ׂ�����̖{���̈Ӗ��ł̑�����l��������ꂽ�B
�b���̂͋��b�I�ȕ��͋C�Ȃ̂ɁA���Ƀ��A���ȕ`�ʂȂ̂���ۓI�ȍ�i�B
�i2010�N2��28���Ǘ��j
-
�w���{�l�̒m��Ȃ����{��Q�x�i���F�֑����C���q�j�m���f�B�A�t�@�N�g���[�n
����ǂ{�̑��e�B�p���[�͐����Ă��Ȃ��Ă܂��܂����Ώo����B
�O���l�����{�i��j���ǂ̂悤�ɍl���Ă��邩���悭�킩��B
���{�l���Č��\����Ȗ����Ȃ̂�������Ȃ��Ɖ��߂Ďv���B
�i2010�N2��22���Ǘ��j
-
�w�C�M���X�̕v�w�́@�Ȃ�����Ȃ��̂��x�i���F��`�c�q�j�m�V�����Ɂn
���{�l�̕v�w�̍l�����Ƃ܂�ňႤ�X�^���X�̃C�M���X�l�B
���r���[�Ȍ_��Љ�ǂ��Ȃ��̂ŁA�O�ꂵ�Ă���C�������ǂ��B
��l�Ԃƈ�l�ԂƂ̊Ԃ̖������c�Ƃ���������O�̂��Ƃ��o���Ȃ����{�Ƃ������B
�i2010�N2��18���Ǘ��j
-
�w�Â��ĖL���ȃC�M���X�̉Ɓ@�֗��ŕn�������{�̉Ɓx�i���F��`�c�q�j�m�V�����Ɂn
���҂̃C�M���X��D���x��������C�ɂȂ邪�A�ǂ݂��̂Ƃ��Ėʔ����B
�Ȃ��Ȃ�A�l���g�������C�M���X�D��������ł���B
�{���ɕ�炵�₷�������Ƃ����̂͂ǂ��������̂��H���l��������ꂽ�B
�i2010�N2��11���Ǘ��j
-
�w�t�B�b�V���X�g�[���[�x�i���F�ɍ�K���Y�j�m�V�����Ɂn
�S�̂��݂��ɊW�Ȃ��Z�ҏW�ł��邪�A����ɗ������̂������Ȃ̂Ŗʔ����B
�\���́u�t�B�b�V���X�g�[���[�v�́A���ɋ������B
�w�l�Ԃ̈��������͓����ƈقȂ�Ƃ���S�����x�Ƃ������t�́A
������҂̕ʍ�i�ɂ��o�Ă�����ۓI�Ȍ��t�B
�i2010�N1��10���Ǘ��j

2009�N
-
�w���n���䂭�i�S�W���j�x�i���F�i�n�ɑ��Y�j�m���t���Ɂn
�Ɛl�������ė��Ė{�I�ɕ���ł����̂ŁA�v�������ĂX������ǂݎn�߂�B
�S�������̎��Ԃ������ēǂ��ƂɂȂ邪�A���X���n�Ɖ�Ċy���������B
���n�Ƃ����l�Ԃ����̎���ɐ�������ՂɊ��ӂ���B
�i2009�N12��28���Ǘ��j
-
�w���{�l�̒m��Ȃ����{��x�i���F�֑����C���q�j�m���f�B�A�t�@�N�g���[�n
���������ɓd�Ԃœǂ�ł��Đ����o���ď������ɂȂ�B
���{��������O���l���甭��������{��ł���Ƃ��낪�ʔ����B
�����āA���߂ē��{�ꂪ�D���ɂȂ�{�B
�i2009�N12��17���Ǘ��j
-
�w���Z�����U������i�P�W�j�x�i���F�O���q���q�j�mBIG SPIRITS COMICS SPECIAL�n
�u�t�F�`������싅�}���K�v�Ȃ̂������ŁA�m���ɊG�̃A���O�����Ɠ����B
�싅���̍g��_�E�s�V���т͂قƂ�ǒ���Ȃ��̂ɁA���ȃL�����B
�����E�C�i�Â��I�j�����߂Ă��̖{��ǂ�ł͂����Ȃ��B
�i2009�N09��01���Ǘ��j
-
�w�x�i�K�N�j�i�P�O���j�x�i���F�Βː^��j�m�r�b�O�R�~�b�N�X�n
�����d�˂�ɏ]���āA�G�O���V�[���������Ă��Ă���B
�R�x����Ƃ��Ă͕�����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��A�l�ԃh���}�Ƃ��Ăǂ�ǂ�ʔ����Ȃ��Ă���B
��S���u�j�̕���v�ł́A�u��ɋ����Ȃ��B�v�Ƃ����䎌�Ƀz�����B
�i2009�N08��31���Ǘ��j
-
�w�R�o��͂��߂܂����x�i���F��Ƃ����j�m���f�B�A�t�@�N�g���[�n
���݂̉̂̒��Ԃ��̂��C�ɓ������Ƃ����̂ōw���B����B�ʔ����B
�т��F�y�����I���������I�������I���q�����C�}�h�L�R�o��R�~�b�N�G�b�Z�C�I�I
���N�͏�����ɂ��ĎR�ɍs���Ȃ������̂ŁA�ǂ��ł���������R�o�肪�������Ȃ����B
�i2009�N08��25���Ǘ��j
-
�w�I���̃t�[���x�i���F�ɍ�K���Y�j�m�W�p�Е��Ɂn
�ɍ��i�ōł��D���ȁw�I�[�f���{���̋F��x�Ɍ�����ׂ邭�炢�ʔ��������B
�W�̘b���ʁX�ɐi�ނɂ�������炸�A�o��l���ɂ���Ĕ����Ɋ֘A���W�J����B
�e�N�j�b�N��I���Ƀe�N�j�b�N�Ƃ��Č����Ȃ���҂̎�r�ɒE�X�B
�i2009�N08��23���Ǘ��j
-
�w�����I���x�i���F���c�p�N�j�m���t���Ɂn
���c��i��ǂ̂́A�w�C���E�U�E�v�[���x�A�w�u�����R�x�Ɏ����łR���ځB
�ǂ̖{�������W�J�ɂ�������炸�A����̖{�͂��܂����������B
���R���N�����P����ʐl�ł͂Ȃ����炩�H�S�b���A��ʐl�̍ŏI�b���ǂ������B
�i2009�N08��07���Ǘ��j
-
�w�_�X�̎R��i���������j�i��E���j�x�i���F���� �сj�m�W�p�Е��Ɂn
�u�Ӑg�̍�i�v�Ƃ����̂͂��̂悤�ȍ�i�������̂��Ǝv���B���������B
�R�x�����Ƃ����̂͏��߂Ẵ`�������W�ŁA���Ԃ��������Ă��܂����B
�ĎR�͑�D�������A�~�R�͂�͂�|���B���Ԃ�ꐶ�o��Ȃ����낤�B
�i2009�N08��05���Ǘ��j
-
�w�z�C�ȃM�����O�̓���ƏP���x�i���F�ɍ�K���Y�j�mNON NOVEL�n
�w�z�C�ȃM�����O���n�����x�̑��ҁB�O��قǂ̖ʔ����͂Ȃ��������H
�������o��l���̃L�����̔Z���͌��݂ŁA���ꂼ�ꂪ���ꂼ��̖���������B
�h�_�o�^���I�ȃe�C�X�g�ɐ^�ʖڂɎ��g��ł���Ƃ��낪���҂炵���čD���B
�i2009�N06��12���Ǘ��j
-
�w�x�i�K�N�j�i�P���`�X���j�x�i���F�Βː^��j�m�r�b�O�R�~�b�N�X�n
�w�O���Ɂu�ǂ��撣�����v���Č���ꂽ���x�c�����̐����������I�I
���L���b�`�R�s�[�B�m���Ɏ�l���̎O���̂悤�Ȑl�Ԃɉ���Ă݂����B
�G�O���V�[���͋��Ȃ̂����A�R���m�����炩�A�Ȃ�������Ȃ�ǂ߂�B
�o�R�̕|�������߂Ċ������B
�i2009�N06��07���Ǘ��j
-
�w�^�b�`�i�S�P�S���j�x�i���F�������[�j�m���w�ٕ��Ɂn
������܂��܁w�^�b�`�x�̎��ʉf����e���r�łn�`���Ă��āA�����Ă��܂��B
�f��̏o�����ǂ��̂����̂ł͂Ȃ������A���̈�ۂ@���邽�߂ɓǂݒ����B
�o���߂��̊������邪�A��i�I��������肭�s�����ǂ���B
�i2009�N05��15���Ǘ��j
-
�w�����x�i���F�ɍ�K���Y�j�m�u�k�Е��Ɂn
�ɍ��i�͑����ǂ�ł��邪�A���̒��ł����Ȃ�ِF�̍�i�B
���{�ł����ۂɂj�������������ɂ߂Ă�������ɏ����ꂽ��i�Ȃ̂ŁA
��҂�����J���Ă����̂͊ԈႢ�Ȃ��B
�i2009�N04��28���Ǘ��j
-
�w�Տ�x�i���F���R�G�v�j�m�����Е��Ɂn
���R��i�œǂ̂́A�w�e���݁x�A�w�������x�A�w�N���C�}�[�Y�E�n�C�x�Ɏ����łS���ځB
�q�`�j���������J�b�R�ǂ����B������Ɨ���l�Ԑ����f�n�n�c�B
�i2009�N04��21���Ǘ��j
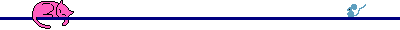

![]()